ヒプノのウソ?ホント
ヒプノセラピー(催眠療法)が、ホントのところどんなセラピーなのか、怪しいのか、根拠があるのか、どんなお悩み、課題を解決できるのか、どういう効果を期待できるのかなど、驚きの事実や具体例をお伝えしています。また、誰でもすぐに実践できる簡単なツールや、意識の整え方もご紹介。
#19 映画「ザ・ボックス」から学ぶ、あがり症とその克服
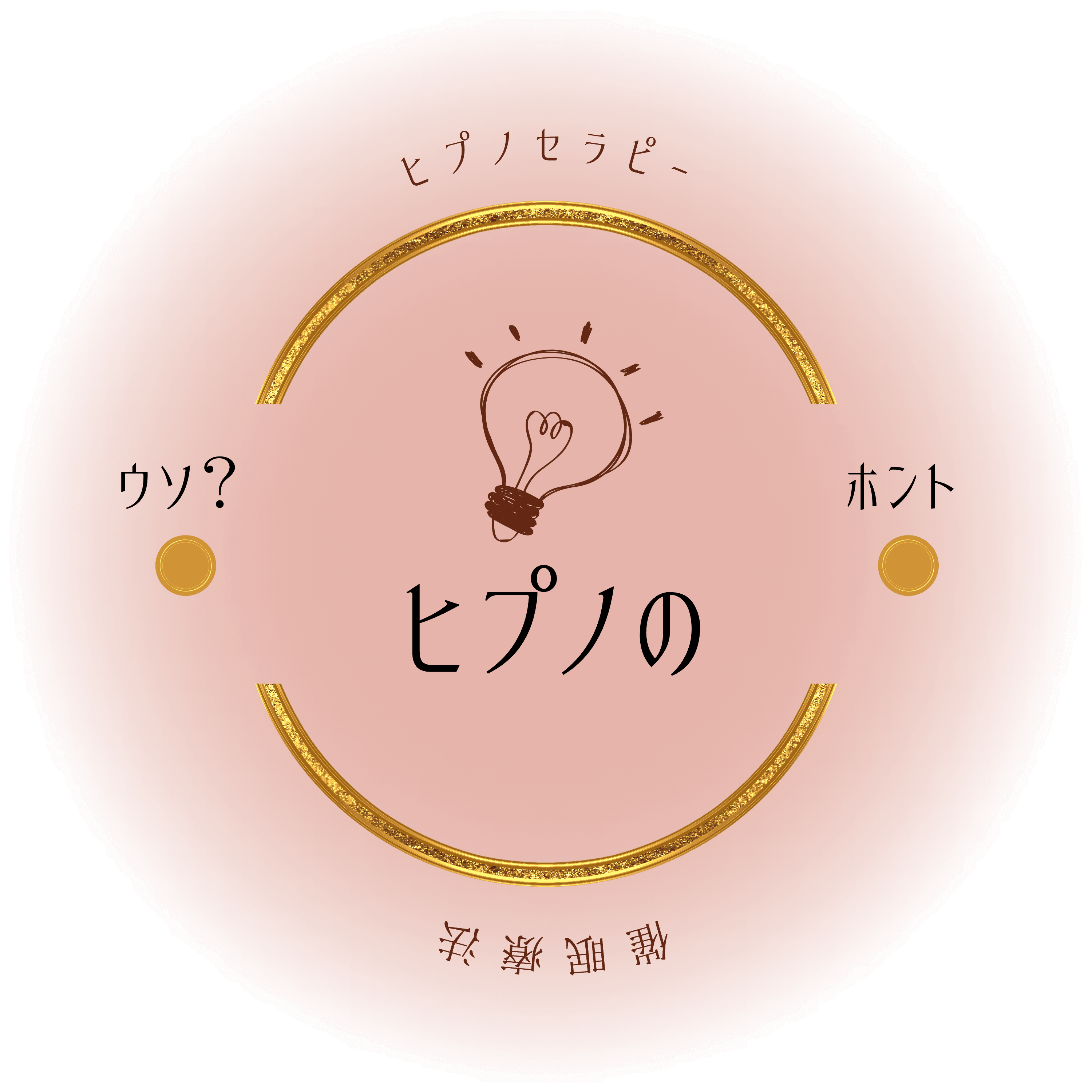
ヒプノのウソ?ホント #19 映画「ザ・ボックス」から学ぶ、あがり症とその克服 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 23:12 Subscribe Share Amazon Anchor Apple Podcasts Spotify YouTube RSS Feed Share Link Embed
購読: Amazon |
#18 日頃から実践できるあがり症対策:呼吸と心拍数のびっくり事実!
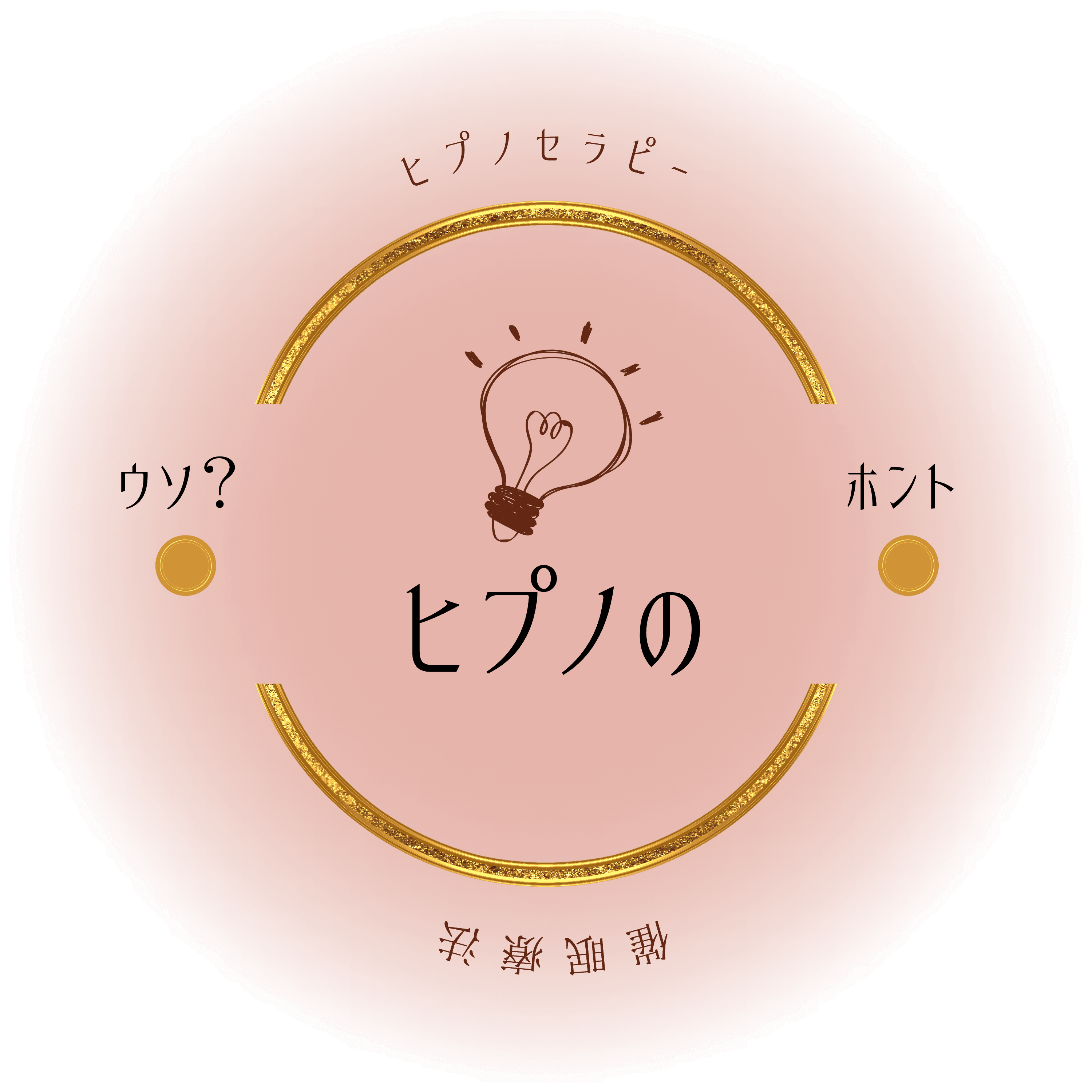
ヒプノのウソ?ホント #18 日頃から実践できるあがり症対策:呼吸と心拍数のびっくり事実! Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 17:52 Subscribe Share Amazon Anchor Apple Podcasts Spotify YouTube RSS Feed Share Link Embed
購読: Amazon |
#17 瞑想 vs. ヒプノのMuse対決
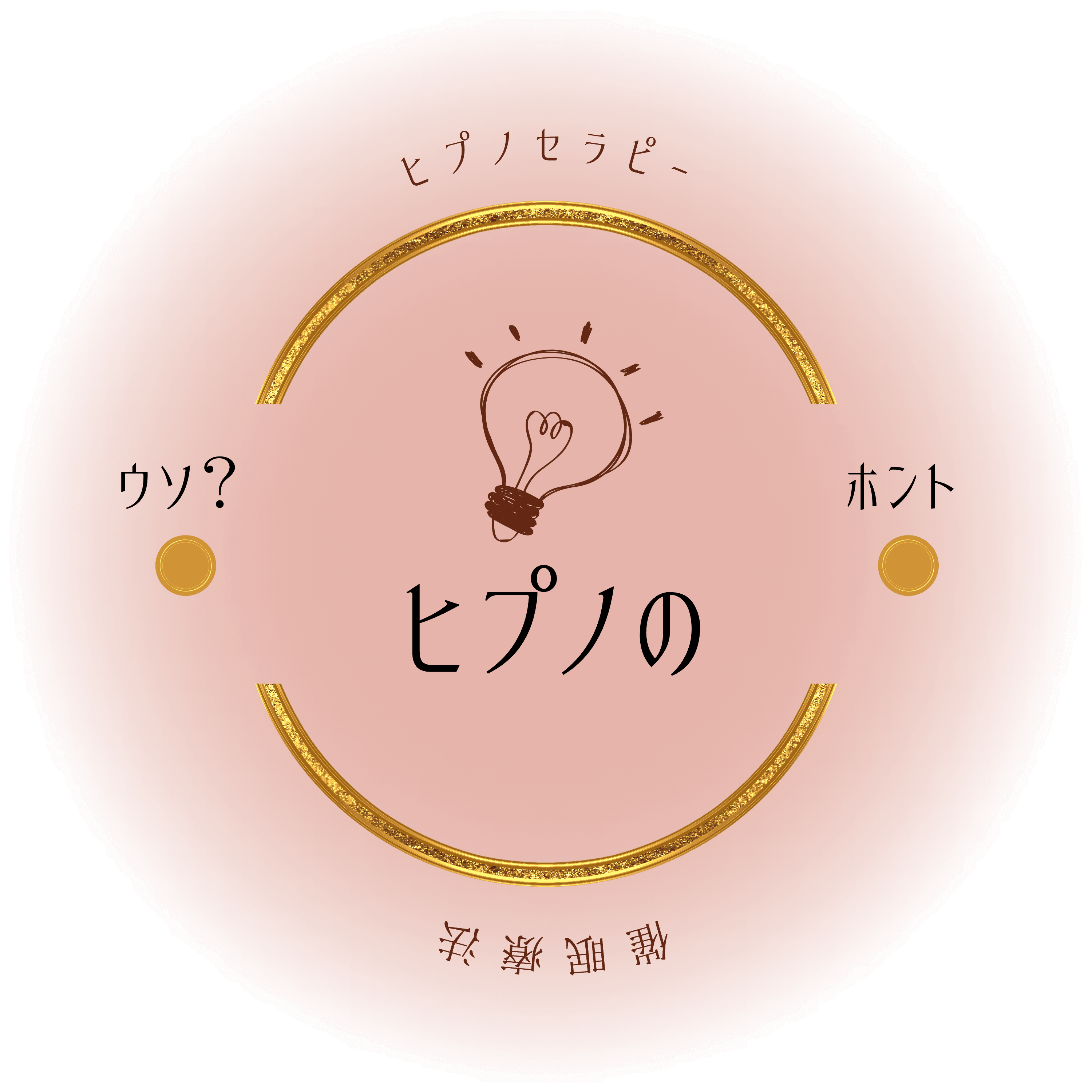
ヒプノのウソ?ホント #17 瞑想 vs. ヒプノのMuse対決 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 25:07 Subscribe Share Amazon Anchor Apple Podcasts Spotify YouTube RSS Feed Share Link Embed
購読: Amazon |
#16 瞑想・催眠は 脳(前頭前野)の筋トレ・アンチエージング
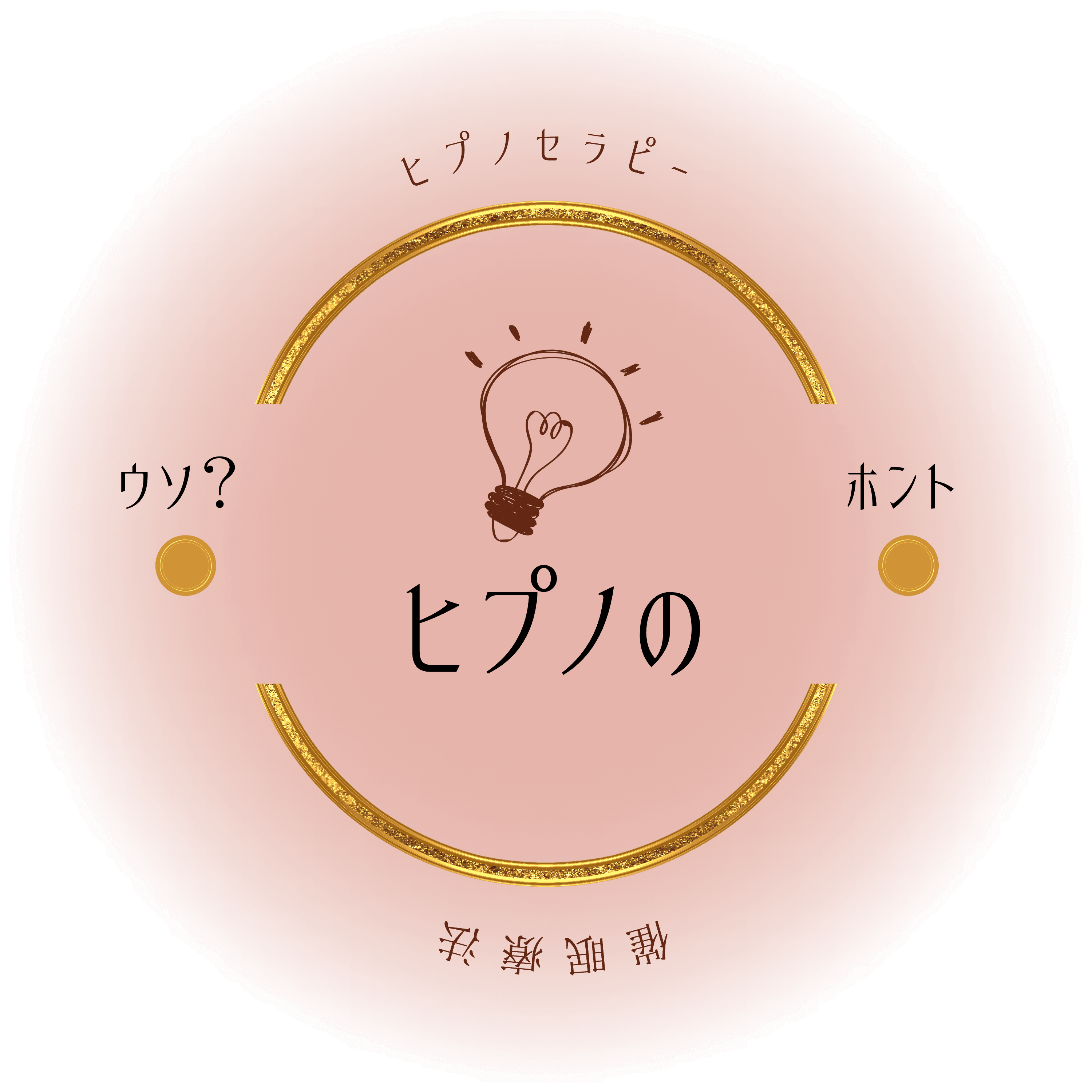
ヒプノのウソ?ホント #16 瞑想・催眠は 脳(前頭前野)の筋トレ・アンチエージング Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 21:57 Subscribe Share Amazon Anchor Apple Podcasts Spotify YouTube RSS Feed Share Link Embed
購読: Amazon |
#15 あがり症は内向的な人に多い?あなたはどのタイプ?
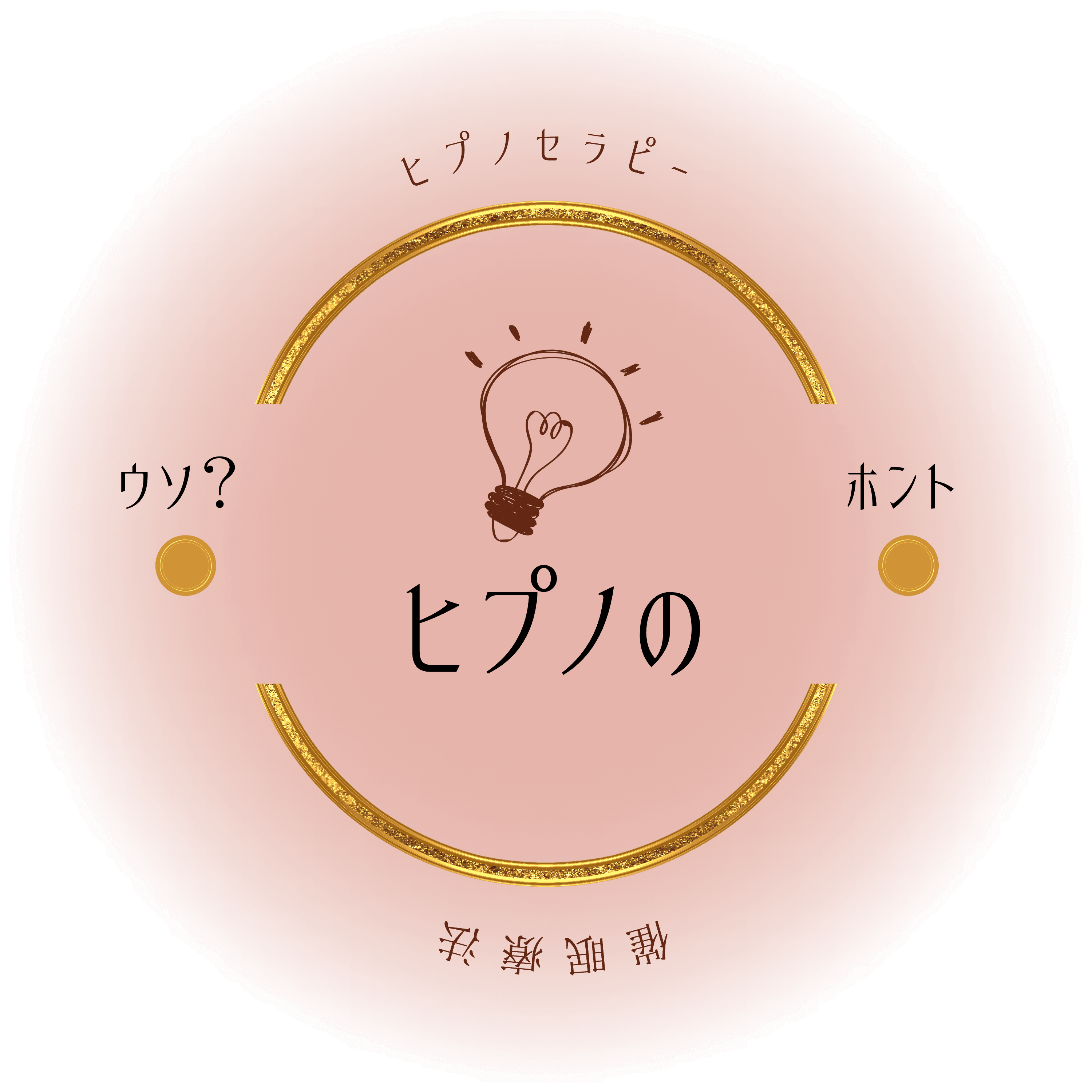
ヒプノのウソ?ホント #15 あがり症は内向的な人に多い?あなたはどのタイプ? Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / Subscribe Share Amazon Anchor Apple Podcasts Spotify YouTube RSS Feed Share Link Embed
購読: Amazon |
#14 あがり症解消の鍵!ヒプノセラピーのリアルな効果をご紹介!
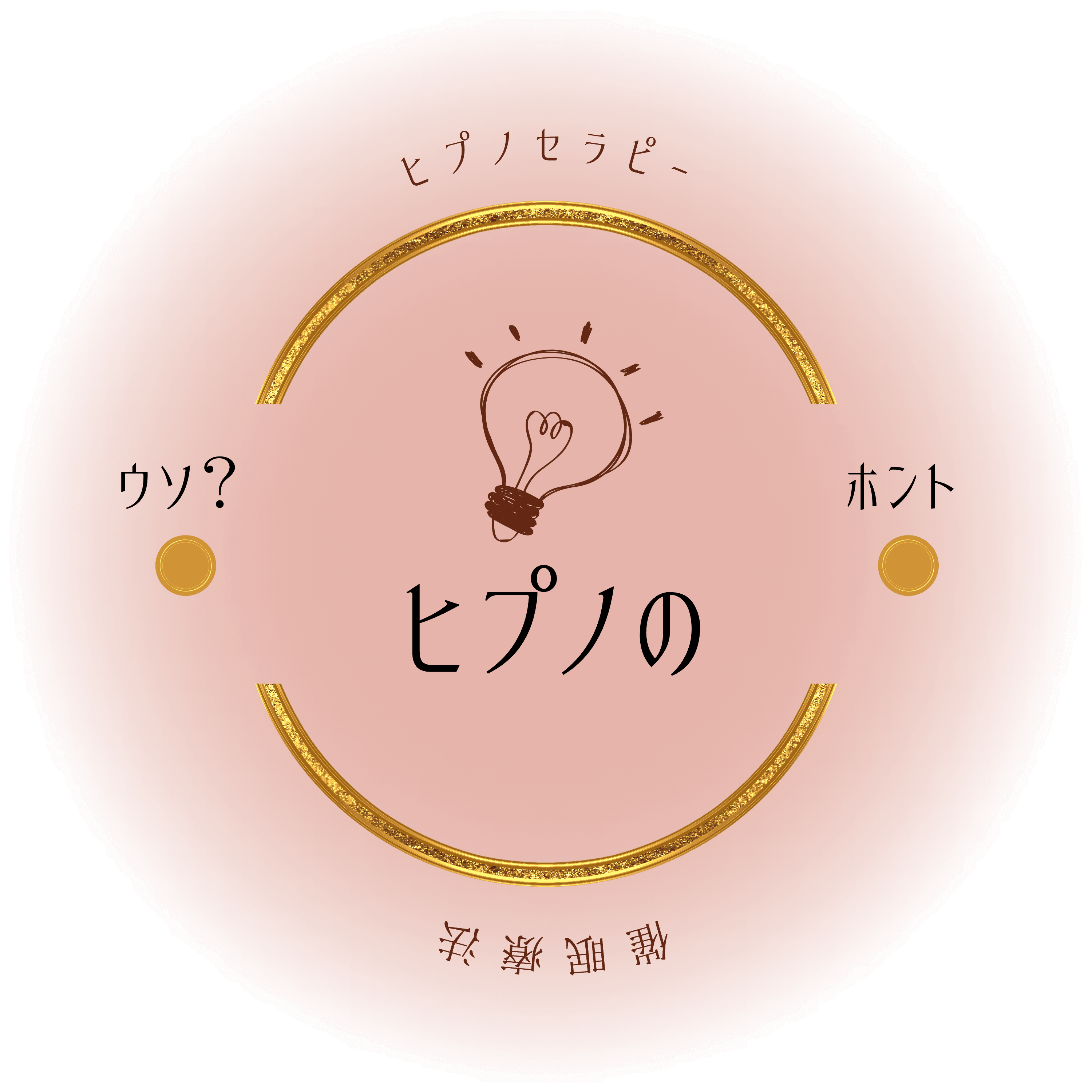
ヒプノのウソ?ホント #14 あがり症解消の鍵!ヒプノセラピーのリアルな効果をご紹介! Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / Subscribe Share Amazon Anchor Apple Podcasts Spotify YouTube RSS Feed Share Link Embed
購読: Amazon |
#13 引き寄せの法則の成功率は常に100%!例外なく誰でもいつでも…
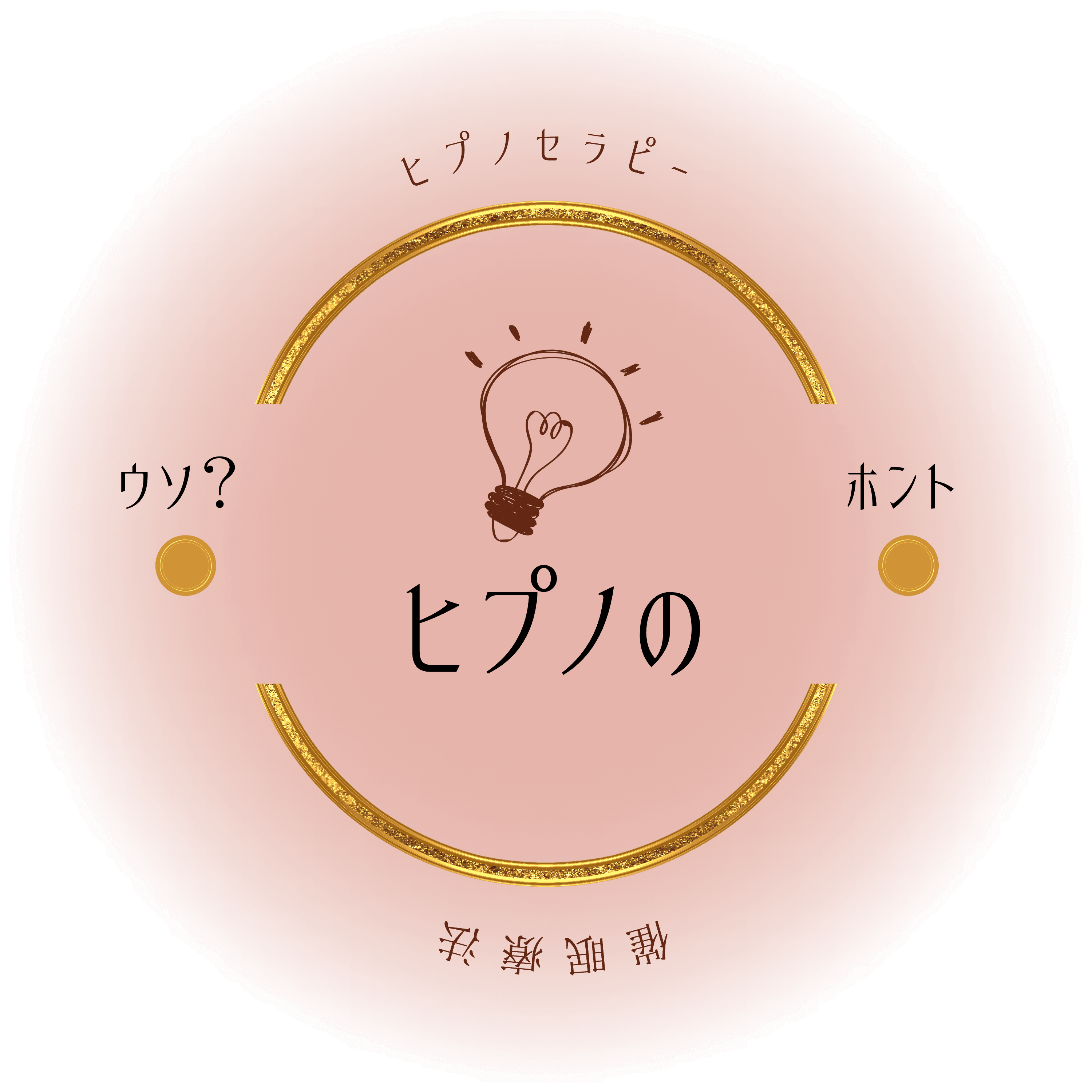
ヒプノのウソ?ホント #13 引き寄せの法則の成功率は常に100%!例外なく誰でもいつでも… Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / Subscribe Share Amazon Anchor Apple Podcasts Spotify YouTube RSS Feed Share Link Embed
購読: Amazon |
#13 引き寄せの法則の成功率は常に100%!例外なく誰でもいつでも…

引き寄せの法則、信じてますか?実践されてますか?うまく引き寄せられていますか? 今回のエピソードでは、引き寄せの法則について新たな視点から解説し、実践的なヒントをご紹介します。
エピソードのポイント
私自身の体験: 不思議なほど「引き寄せ」に長けていた! 引き寄せられなくなった時期 「引き寄せの法則」との出会い うまくいかな〜い! ヒプノとの出会い あ〜、だからうまくいかなかったのか・・・ 顕在意識と潜在意識の足並みは揃ってる? 網様体賦活系の仕組み 引き寄せの法則は「常に」働いている! あなたが引き寄せているのは?スクリプト
ヒプノの嘘・ホント、エピソード13へようこそ。
前回、毎月未来ペーシングをされている方について触れた際に、引き寄せの法則と思われるかもという話をしました。
引き寄せの法則、信じてますか?そんなもの存在しないと思われる方もいらっしゃるんだろうなぁと思います。私は、子供の頃、引き寄せがとても上手でした。もちろん、引き寄せの法則なんて知りませんでしたし、当時はそんなコンセプトも知られていなかったと思います。はい、そのぐらい昔々の話です。
でも、「自分が欲しいと思うものは自然と手に入るなぁ」とよく思っていました。例えば何かが学校で流行り出して、「あ〜、いいなぁ、私も欲しいなぁ」と思っていると、何かのイベントでもらえたり、おねだりをして親に買ってもらうとかいうのではなくて、まるであっちから飛び込んでくるように手に入ったんですよね。くじ運は全くと言ってないので、抽選で当たるとかいうのでもなく。不思議だけど、そんなものなのかなぁなんて思ってました。事実、誕生日のプレゼントに何が欲しい?と母親に聞かれた時に・・・「特に何もない」って答えたことがあるのも覚えています。もちろん、毎年のことではありません。
今思うと、私は網様体賦活系を活用するのが得意だったのかなぁなんて思います。それは実際、大学卒業するくらいまで続きました。それは、何でもかんでも自分の思い通りにいく、願いが叶うということではなく、常にどこかで「願ったことは実現できるものだ」みたいな根拠のない確信みたいなものがあったんですよね。それは別に意識してるわけではなく、私の潜在意識の中にあったんだと思います。
それがガラッと変わったのは、アメリカでの生活の最後の3年ぐらい。13年もアメリカにいたのも、アメリカの生活が大好きだったからで、当時は何とかアメリカに住み続ける方法を探そうとしていました。一旦は労働ビザを取得したものの、また大学院に戻ることを決めたりしたこともあり、また母が癌を患って一時帰国したりしたこともあり、最後の3年は日本とアメリカを行ったり来たりしながら、本当に「何をどうやっても絶対にうまくいかないことってあるんだな」っていうことを実感し、また、「流れに任せる」っていうことも時には大切なんだなぁということを学んだ時期でもありました。
最終的には帰国したわけなんですが、日本での生活に馴染むのにはとても時間がかかりました。最初の数年間は、如何にこの国を出るか、どこか移住できる国はないか、そんなことばかり考えていたんです。考え方もちょっと後ろ向き。元々「グラスに半分も水が残っている」と思うタイプだったのが、「グラスに半分しか水がない」思考に陥っていたと思います。
帰国して数年経った時に、アマゾンのサイトを見ていて、ふとThe secretという本が目に入りました。2006年に出版されてアメリカでベストセラーになったので、その1年後ぐらいのことかな。子供の頃から本の虫だった私ですが、好きなのはフィクション、特に推理小説やSF。なので普段ならフィクション以外は見向きもしなかったんですが、このシークレットっていうタイトルだったのか・・・何か気になって、ポチっていました。届いた本を開いてみて・・・ん〜 なにこれ?エッセイ?明らかに自分が好む系じゃないと思ったものの、数ページを読み始めたら・・・数時間後には読み終えていました。
この本で、初めてlaw of attractionについて知りました。で、その時に思ったんですよね・・・あ、子供の頃経験してたのはこれだったんだって。
でもですよ・・・やってみようと思ってもうまくいかない。全然引き寄せられない。子供の頃はうまくいったのに、何でだろう?と不思議に思いつつも、また、子供時代の経験から引き寄せは存在するとわかっていつつも、でも思ったように使えないじゃん・・・みたいな感じで、活用できてはいませんでした。
今思えばですよ、フィクション以外に興味がなかった私が、それまで見向きもしなかったAmazonのリコメンド機能で勧められていたこの本が気になったこと自体、引き寄せだったんじゃないかなぁなんて、思ったりもしますけどね。
いづれにしろそこからまた長い年月が経ち、ヒプノセラピーを勉強し始めて、その謎が解けました。引き寄せの法則は間違いなく存在します。だって、私たちの脳の中にそのメカニズムがあるんですから。実際、私たちは常にいろんなものを引き寄せています。問題は、自分が顕在意識で望んでいるものを引き寄せているかっていうところですよね。
というのも、顕在意識で自由自在にコントロールできるものではないから。だから、顕在意識レベルだけで引き寄せようとしてもうまくいかないことが多いんです。
うまくいかないことが多い・・・ということは、うまくいくときもあるっていうことです。じゃあ、何が違うのか。もうお分かりかもしれませんが、潜在意識と顕在意識が同じ方向を向いているか、足並みが揃っているかどうかです。
ヒプノセラピーのセッションをしていると、「潜在意識と顕在意識の足並みが揃うってこういうことなんですね!」というコメントをいただくことがあります。ん、確かに、足並みが揃っているのかどうかって、自分ではなかなか分かりにくかったりしますよね。
潜在意識は基本的に「未知」を嫌います。未知、知らないこと、経験していないことというのは、結果がどう転がるか分かりませんので、「自分の身を守る」ということが大きな役割である本能を含む潜在意識は、リスクとして未知を嫌います。たとえ結果が良くなかったとしても、結果がどう転がるかわからないよりはマシと判断するぐらい、未知を避けようとする。
だから、初めてのことには緊張するわけです。どう転がるかわからないから。そしてその結果がどの程度自分にとって重要かによって、または、どのくらい関心が高いかに
#12 2024年の抱負、それを達成する戦略とコツ!
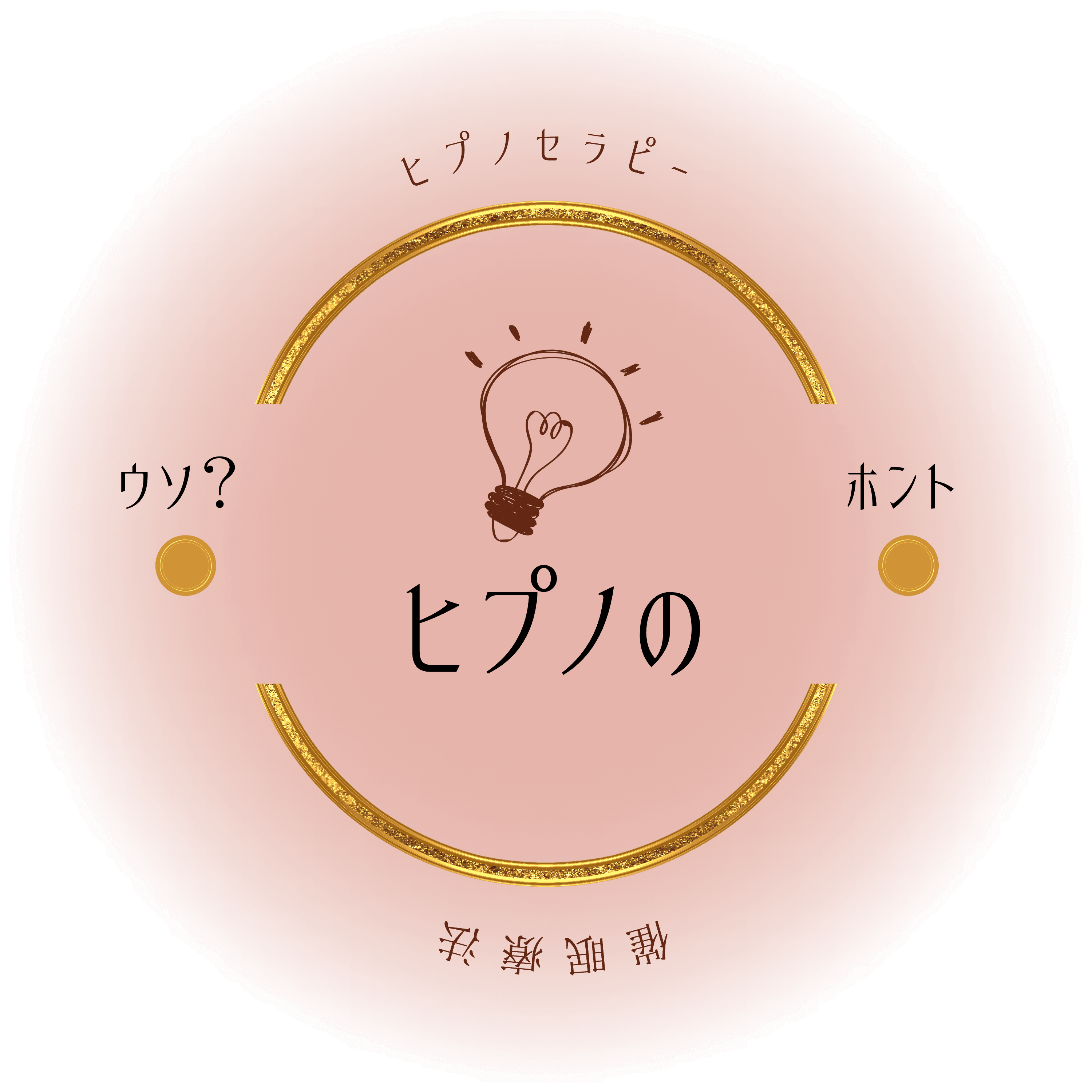
ヒプノのウソ?ホント #12 2024年の抱負、それを達成する戦略とコツ! Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / Subscribe Share Amazon Anchor Apple Podcasts Spotify YouTube RSS Feed Share Link Embed
購読: Amazon |
#12 2024年の抱負、それを達成する戦略とコツ!

新年明けましておめでとうございます! 2023年はご自身にとってどんな年でしたか?2024年はどんな年にしたいですか? 今年からは抱負を「年初に思い描く夢」に終わらせず、達成するための戦略とコツをお伝えします。
エピソードのポイント
2023年の振り返り、そして2024年の抱負 抱負を達成するコツ 抱負を書く:未来ペーシングのコツ 違和感を感じたら 現実味チェック 違和感は潜在意識からのヒント! アファメーション メンタルバンクスクリプト
ヒプノの嘘・ホント、エピソード12へようこそ。
2024年、明けましておめでとうございます。 今年もどうぞよろしくお願いします。
さて、新年を迎えるにあたって、2023年を振り返られましたか? 私にとっては、結構激動の一年でした。 家族の大怪我、緊急入院が立て続けに起きたり、そのストレスのせいか自分自身体調を崩したり、大学院の恩師が亡くなったり。
でも悪いことばかりではなく良いこともたくさんありました。家族の絆が強くなった側面もあり、また自分自身の体と心の健全性、ウェルビーイングをあらためて見つめる機会にもなったり、またヒプノの学校を卒業後、ちょっと疎遠になってしまっていた友人たちと定期的にZoomやメールで連絡を取るようになったり、そしてより多くのクライアントさんにヒプノセラピーを知ってもらうことができたり。
チャレンジも多かったけれど、得るものも大きかった年と言えるかもしれません。 実際、人生ってそういうものですよね。山あり谷あり。冷たい強風に震えることもあれば、ポカポカ陽気に心も体も温まることもある。
辛い時期の真っ只中にいると、「いつかは終わりがくる」「楽しい時期がまた必ず来る」とは到底思えないこともあるんですが、でも最低でも「この経験から何か学べるもの、得るものがあるはず。というか何かしら絶対得てみせる」みたいな負けん気?、そんなところも私にはあります。
そんなわけでプラマイ色々あった一年ではありますが、じゃあ2024年、どんな年にしようかなぁ・・・ご自身はどうですか?2023年はどんな年で、2024年はどんな年にしたいですか?
新年の抱負を決める時に、何か例えば資格取得だったり、昇進だったり、具体的な成果をえる目標を立てると言うやり方もありますが、終わった年を振り返って、新年の自分はどうありたいか、どう変わりたいかを目標にするというのも、ありですよね。
今年の私の抱負は後者で、より最適な「バランス」の取り方を身につける年にしたいと思っています。バランスってもう昔から私にとってはキーワードではあって、何か決断する時には必ず考えることではあるんですが、昨年はいろんな出来事によって自分の体調やマインドが左右されたのは事実。なので、より内面を強化することでより上手にバランスを取れるようになりたいなぁというところです。イメージは天秤。その時々でちょっと右に傾いたり、ちょっと左に傾いたりしながら、常にその時に最適なバランスを取れるように。
先日、私がよく聞いているポッドキャストのホストが、彼女の新しいキーワードは「ハーモニー」つまり調和だと言っていました。彼女のイメージではバランスは「半々」なんだそうです。つまり仕事もプライベートも半々とか。でも彼女が目標としているのは必ずしも半々ではないから「ハーモニー」調和って説明してたんですね。
これって、面白いなぁと思いました。やっぱり人って言葉の意味やニュアンスも少しづつ違うものですよね。確かにバランスって元々は2つのものの重さを押し測るツール、つまり天秤などをバランスと呼んでいたんですよね。当然のことながら、左右のお皿の位置が同じ高さ、釣り合いが取れている時は比較している2つのものの重さが同じということで、つまり「バランスが取れている」ともいうわけです。だから、彼女のいう半々っていうのはその通りなんですよね。それにハーモニーと言う言葉の方が何か全てが丸く治る的なほんわかしたイメージもあります。なので、ハーモニーのキーワードもいいなとは思ったんですが、私は恒常性というか、こう常にバランスを取るべくシーソーのようにゆらゆらしているイメージから、「バランス」という言葉をキーワードに選びました。
これって、自律神経の仕組みと同じなんですよね。交感神経と副交感神経は、いつどの時点でもどちらか片方だけが働いているわけではないし、常に体内の環境や外部の環境の変化に応じて、より交感神経に傾いたり、副交感神経に傾いたり。ゆらゆら揺れつつ、常に調整しながらバランスを取っている。オーラリングのデータを見ていると、このシーソー状態がよりわかりやすく見えて面白いです。そして、より自分の心や体の変化に敏感になって、より良いバランスが取れるようになることで、それが私にとってのハーモニーにもつながるかも?何が起きても動じない。表面的に動じないだけではなくて、内面も柔らかに、柔軟に衝撃を吸収して、本来の姿に戻れるみたいな。
じゃあ、どうやってこの抱負を実践、達成するか・・・ですが。 まず、文章にして書き出します。普段から手書きがお好きな方は手書きがオススメ。私のように手書きって、何かしらの手続きで住所や名前を書くぐらいしかしませんっていう人は、普段使い慣れている入力方法でOKです。
手で書く、入力するという言動は、潜在意識に直接つながっています。子供の頃、漢字の練習や九九なんかも、必ず書いて練習するように言われましたよね?その方が断然記憶に残る。つまり潜在意識に落ちやすいわけです。この際に、もうすでに実現したかのように現在形で書きましょう。例えば、私の場合なら、自分の心と体からのシグナルを敏感に感じとれるようになったことで、自分自身をプッシュする時、しない時、長めに休息を取る時など、その時々で自分にとってなにがベストなのかを見極めてバランスを維持することもできるようになった。みたいな。実際には、さらに詳細を膨らませて書いていきますが、イメージ的にはそんな感じ。
実は、あるワークショップで、毎月翌月の未来ペーシングをしているという人がいました。その方は翌月に達成したいことを、まるでもうすでに実現したかのように現在形で書き出すんだそうです。で、書き出したらあとは見もしない。そのまましまってしまうんだそうです。で、月末に翌月の未来ペーシングをする際に前月に書いた内容を取り出して確認してみる。そうすると、「何を書いたのか覚えてもいないけど、今月は多分全然実現できてないな」と思っても、実際に見てみると、ことごとく実行してる、実現しているんだそう。もう何年もこの未来ペーシングをされているとのこ
#11 プライベートの人付合いは楽しいけど、仕事上のお付合いは自分らしく楽しめない?3つのツールで克服しよう!
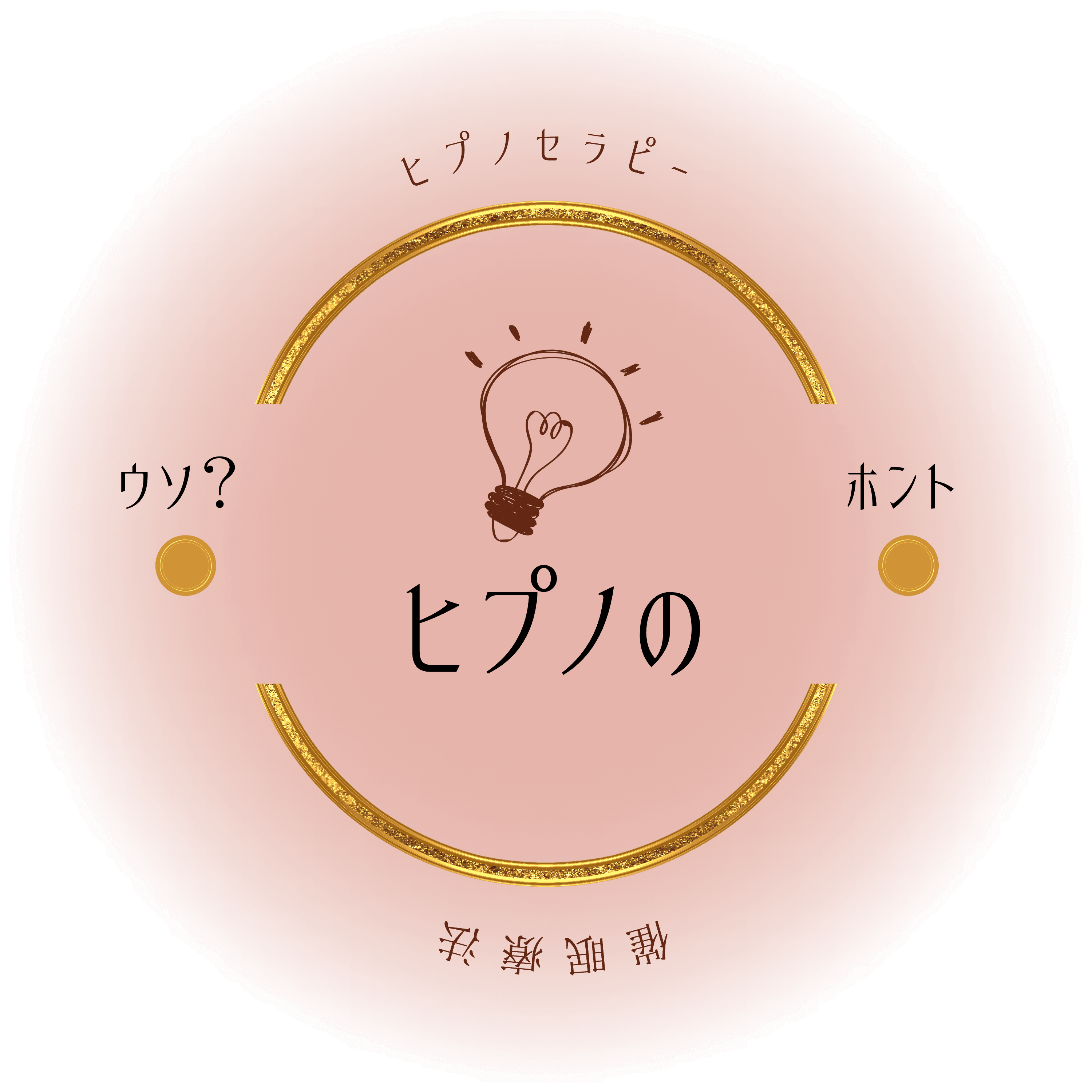
ヒプノのウソ?ホント #11 プライベートの人付合いは楽しいけど、仕事上のお付合いは自分らしく楽しめない?3つのツールで克服しよう! Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / Subscribe Share Amazon Anchor Apple Podcasts Spotify YouTube RSS Feed Share Link Embed
購読:
#11 プライベートの人付合いは楽しいけど、仕事上のお付合いは自分らしく楽しめない?3つのツールで克服しよう!

いよいよ2023年も残り2週間。そろそろ忘年会シーズンですね。
忘年会といっても色々…プライベートの知人・友人との会食もあれば、仕事上でのお付き合い的な会食まで。
知人や友人との会食では自分らしく、楽しく時間を過ごせるのに、職場や仕事上のお付き合いになると、なんだか居心地が悪く、何を話せば良いのかもわからないし楽しめないなんて感じたことはありませんか?
今回は、職場や仕事上のお付き合いでも普段の自分らしさで時間を過ごせるようになる方法についてお伝えしています。
このエピソードのポイント
「プライベートでの自分らしさ」を「リソース」として活用する 潜在意識は「未知」を嫌う プライベートで感じるプラスな感情の紐付けを、仕事上の人付き合いのイメージにくっつけよう! 行動変化のレイヤー アファメーション イメージ療法:リソース状態の活用 筋トレ効果 小さなステップ、小さな成功体験の積み重ねが大切 職場で大きな人間関係のストレスを抱えていたり、業務に支障が出ているなら…スクリプト
ヒプノの嘘・ホント、エピソード11へようこそ。
いよいよ2023年も残り2週間となりました。もうそろそろ忘年会が始まるころでしょうか。 忘年会も色々ですよね。プライベートの知人・友人との会食もあれば、仕事上でのお付き合い的な会食まで。
知人や友人との会食では自分らしく、そして楽しく時間を過ごせるのに、職場や仕事上のお付き合いになると、なんだか居心地が悪く、何を話せば良いのかもわからないし楽しめないなんて感じたことはありませんか?
今日は、職場や仕事上のお付き合いでも普段の自分らしさで時間を過ごせるようになる方法についてお伝えしましょう。
今回の場合は、プライベートでの人付き合いは楽しめる、自分らしくふるまうことができるということで、これを「リソース」状態として活用します。
どういうことかというと、潜在意識は「未知」、つまり今まで経験のないことを嫌う傾向があります。新しいこと、初めてのことにチャレンジするときに緊張するのは、「今までやったことがないこと」は結果がどう転がるかわからない、つまり未知なので、潜在意識は本能的に「リスク」として捉えます。潜在意識は常に自分自身を守ろうとしているということの表れでもあります。ただ、そこにロジック、論理がないので、顕在意識で「リスク・・・ないでしょ」っていうことでも潜在意識はリスクと感じるんですよね。
リスクというのは何も大ごとではなく、嫌な思いをする、自分にとってマイナスな経験ということです。子供の頃からワンコやニャンコと育った人であれば、犬や猫のイメージに対して「可愛い」とか「楽しい」とかプラスな感情が紐づいていると思いますが、小さい頃に噛まれたり、引っ掻かれたりしたら、「怖い」「痛い」「危険」などのマイナスなイメージが紐づいていルカもしれません 。
じゃあ、子供が初めて馬に触れ合う機会があったとしましょう。犬や猫に比べたら格段に大きい動物、子供の目線からすれば、そして特に8歳、9歳ぐらいまでは潜在意識むき出しの状態ですから、この経験がプラスに転がるのか、マイナスに転がるのかわからないわけですよね。わからないということは、マイナスに転がる可能性がある、つまり痛い思いをするかもしれない、怖い思いをするかもしれない・・・と潜在意識は警告をするわけです。
初めてサンタクロースを見た子供が怯えたりするのも同じメカニズムですね。潜在意識は未経験のことを嫌うんです。でも、一旦、プレゼントもらって、抱っこしてもらって、周りの人がみんなニコニコしていると、「プレゼントもらって嬉しい」「楽しい」とプラスの紐付けができたりします。
さて、話を戻して・・・プライベートでの人付き合いは楽しめる、自分らしくふるまえるということは、「人付き合いは楽しい」「よく知っている人たちとであれば自分らしくふるまえる」という経験が「既知」、つまり潜在意識がすでに知っている内容で、かつそのイメージに対して楽しい、リラックスできるなどのプラスな感情が紐づいているということです。なのでこの紐付けを「リソース」として活用するわけです。
ただ、すでに仕事上のお付き合いでは「居心地が悪い」「自分らしくふるまえない」と感じているということは、職場や仕事上での人付き合いというイメージに対して、「つまらない」とか「居心地が悪い」とか「窮屈に感じる」とか、何らかのマイナスの感情がすでに紐づいているということなので、その紐付けを置き換えるのに少し時間はかかります。
具体的にどうするかというと、ここでも前回お伝えした、行動変化のレイヤー、イメージ療法、そしてアファメーションを活用します。これらの3つのツールは、「意志の力」ではどうにもならない気持ちの問題、そこからくる言動パターンを、ご自身で変えるのにとても有効ですので、ぜひ、いろんな場面で応用していただければと思います。
まずは行動変化のレイヤー。ご自身のアイデンティティ、自己イメージを変えていくというところから始めましょう。前回のエピソードをお聞きになっていない場合は、ぜひ聞いてみてくださいね。この場合はたとえば、「私は誰とでも、誰といても自分らしくふるまえるタイプ、会話を楽しめるタイプ」とか、ご自身にとって一番しっくりくる、または望んでいる自己イメージを選んで、常にその自己イメージを意識するようにしましょう。ことあるごとにマントラのように自分の中で、口に出す必要はないので唱えると良いですね。朝一番、起きて鏡を見た時にその自己イメージをつぶやいてみるのも良いと思います。反復すればするほど、その自己イメージが潜在意識に落ちていきます。前回もお伝えしましたが、違和感があっても気にしない。嘘っぽく聞こえても気にしない。反復することで慣れていき、当たり前になっていって、それが事実になっていきます。
そして、例えば同僚とランチに行くとか、カジュアルで特に普段から緊張することもないような状況でも、「ほらね、自分らしくふるまえているでしょ」と自己イメージを補強すると良いですね。このような「小さな成功」が積み上がっていくと、より新しい自己イメージが補強されて、大きな成功につながっていきます。この、「小さな成功体験」の積み重ね、とっても大切です。これなしに大きな成功はないと言っても過言ではないくらい。
ちょっと緊張する・・・とかちょっと居心地悪いなぁ・・・と感じることがあったら、やはり新しい自己イメージのマントラを唱えてみましょう。「誰といても自分らしくふるまえるタイプだから・・・」と考え
#10 この時期、気持ちの余裕がなくなりがち?緊張をコントロールして実力を発揮するコツ
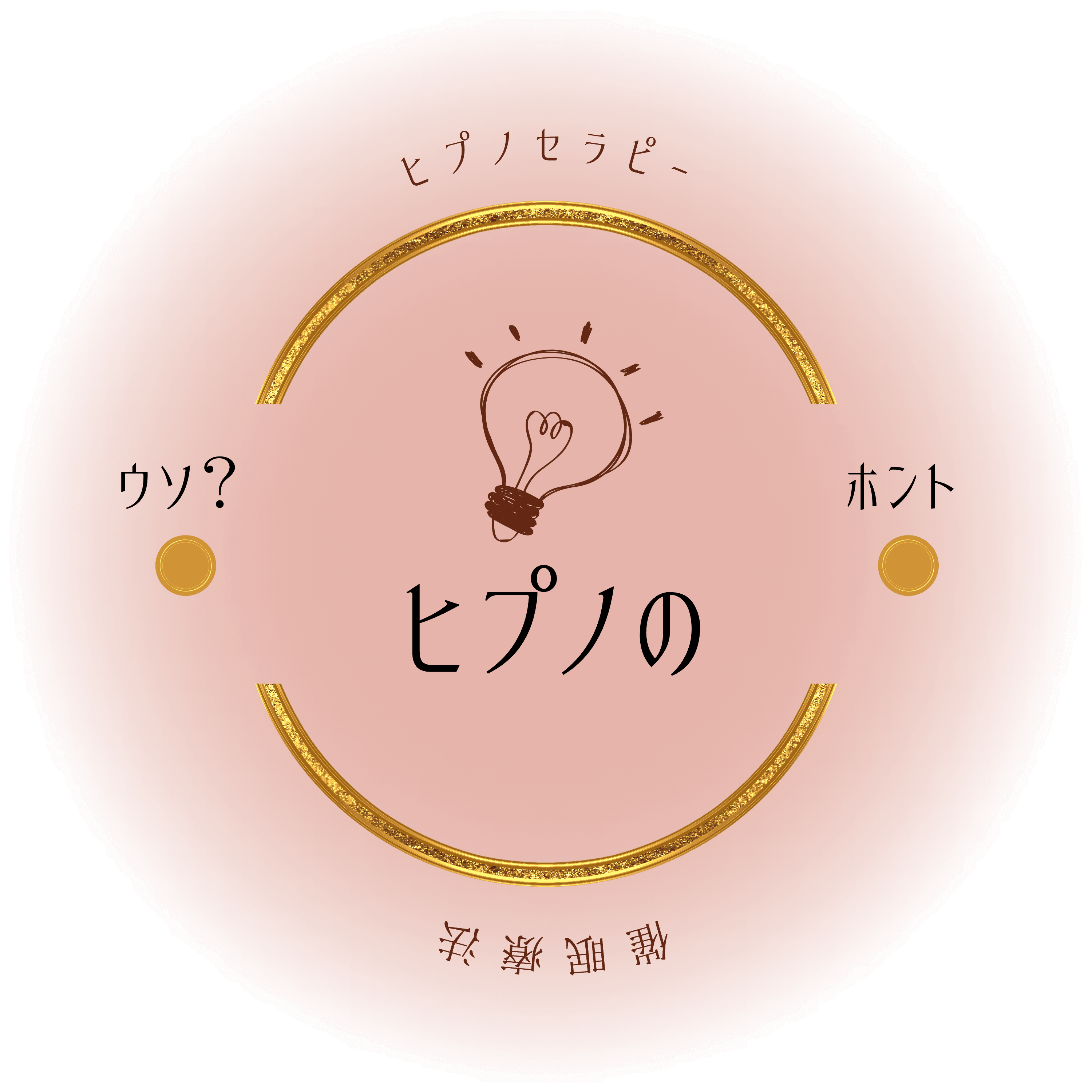
ヒプノのウソ?ホント #10 この時期、気持ちの余裕がなくなりがち?緊張をコントロールして実力を発揮するコツ Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / Subscribe Share Amazon Anchor Apple Podcasts Spotify YouTube RSS Feed Share Link Embed
購読: Amazon |
#10 この時期、気持ちの余裕がなくなりがち?緊張をコントロールして実力を発揮するコツ

クリスマスやお正月、忘年会など楽しいイベントも多い季節。あまりの忙しなさから、気持ちに余裕がなくなったりしていませんか?そして、イベントなどの機会で人前に立つことがあると、普段、特段ひどいあがり症ではなくても、すごく緊張しちゃうなんていうこともあるかもしれません。そして、そういう一度の経験から、恐怖症にまで発展してしまうことさえあります。
意識の仕組みを理解していれば、ご自身で上手に緊張をコントロールして、自分の実力を発揮することは十分に可能です。今日は、この特に忙しない時期、あがり症を乗り越えるためのコツを紹介します。
このエピソードのポイント
準備のコツ 特に出だし、スタートが鍵を握る スピーチやプレゼン自体の準備だけでなく、心・意識の準備も大切 行動変化のレイヤー イメージ療法 アファメーション 本番前夜の睡眠の重要性と脳のリセット より早く効果を実感したいなら…スクリプト
ヒプノの嘘・ホント、エピソード10へようこそ。
いよいよ12月。年末はクリスマスやお正月、忘年会など楽しいイベントも多いですが、あまりの忙しなさから、気持ちの余裕を失ったりすること、ありませんか?そして、イベントなどの機会で人前に立つことがあったら、普段、特段ひどいあがり症ではなくても、すごく緊張しちゃうなんていうこともあるかもしれません。そして、そういう経験から、恐怖症にまで発展してしまうことさえあります。
緊張すること自体は、ごく自然な生理現象で、必ずしも悪いことではありません。慣れていないこと、今までしたことがないことは、潜在意識は「リスク」として捉えるため、交感神経が優位になってリスクに備えようとします。そして、一定程度の緊張であれば、逆にパフォーマンスが良くなったりもします。
ですが、気持ちに余裕のない状況だと、過度に緊張してしまったり、集中できなかったりする可能性が高まりますよね。意識の仕組みを理解することで、ご自身で上手に緊張をコントロールして、自分の実力を発揮することは十分に可能です。今日は、この特に忙しない時期、あがり症を乗り越えるためのコツを紹介します。
まずは準備についてです。これは言わずもがなではありますが、やはり自分のプレゼンやスピーチに自信を持つためにも、丹念に準備をして、それを練習することは必要不可欠ですよね。ただね、その準備にもコツがあります。
これは私自身のあがり症からの経験なのですが、私は大学と大学院で音楽を専攻していました。楽器はピアノだったのですが、大学までは人前で演奏するなんて年1回の発表会ぐらいでしたので、大学に入って月1とか、数週間に1回のペースでステージに立つっていうのは結構なストレスでした。しかも、渡米したばかりでしたから、英語もおぼつかない、アメリカでの生活にも全然慣れていない・・・そんな状況で授業が始まり、ステージにも立つようになったので、そのストレスたるや・・・まさに「余裕ゼロ」の状態だったわけです。
でも逆に、特に1年目は英語があまり理解できなかったということがプラスにも働いた部分もありました。演奏することでコミュニケーションをとるみたいな?友達もまだいなかったし、そもそもまだまだ英語でのコミュニケーションがおぼつかなかったので、練習室にこもっていたため、準備は十分していたというのもあります。
それでも、最初は本当に及び腰でした。当然と言えば当然なのですが、舞台袖では心臓バクバク、手も震えて頭の中は「どうしよう」「どうしよう」がぐるぐる巡ってる感じ?ですが、怖いわけではなかった。プレッシャーが少なかったからですかね。ま、生徒だし。一年生だし。留学生だし、みたいな。そして一旦、ステージに出て、椅子に座って弾き始めると、後は没頭できたんですよね。緊張が完全に解けたわけではないんですが、緊張しつつも、弾いている曲に集中できたということです。
その経験から、特に出だしの練習が大切と私は思っています。準備はもちろん最初から最後までしっかりやるのですが、練習する際は特に出だしの部分に重点を置いて行うと、始めてしまえばなんとかなる場合も多いです。逆に出だしでこけるとあとあとまで引きずる。
また、毎回ではありませんが、フロー、ゾーンとも呼ばれたりしますが、の状態に入れることもあります。マラソンなどのランナーズハイと同じ状態ですね。時間を忘れるほどに没頭する状態ですから、あがり症の症状を感じにくくします。
ただし、あがり症を通り越してステージ恐怖症のレベルまで行ってしまうと、また別のアプローチが必要になってくると思います。というのは、もはや人前に立つことすら無理!という場合は、無理強いすることで恐怖症が悪化する可能性が高くなりますので、もっと小さなステップに分解して徐々に慣らしていく必要があります。このようなケースについては、また別の機会にお伝えしたいと思います。
準備といえば、実際のプレゼン、スピーチの準備だけではなく、心、意識の準備も整えていくことが大切です。普段はあまりあがらない、緊張しないという場合は、ここまでにお話しした準備だけで十分だと思います。ですが、普段から人前に出ると緊張する、すごくあがってしまうという場合は、行動変化のレイヤー、そしてイメージ療法とアファメーションを活用して心と意識の準備をしていきましょう。
まずは行動変化のレイヤーについてですが、ここでダーツの的をちょっと思い浮かべるか想像してみてください。的の中心、小さな円の部分、これがご自身のアイデンティティ、中核部分、自己イメージの部分です。そしてそのすぐ外側の円がプロセス、言動の部分、そして一番外側の円が結果と思ってください
どういうことかというと、自分自身のアイデンティティ、自己イメージをもとに私たちは行動し、その行動の結果が現実として現れるということなんです。そしてこの自分自身、自己イメージをもとにした行動というのは多くが潜在意識からきています。無意識な反応とか言動、仕草とか。
で、結果を変えたいって思う時って、行動を変えようとするのがほとんどなんですよね。でもそれって、そもそも自分のアイデンティティに沿っていないと続かない、結果は変わらなかったりするわけです。
重要なのはダーツの的の中心にある自分のアイデンティティ、自己イメージが変わること。この部分が変わると、自然と言動が変わってきます。言動が変わるから結果が変わる。
芸能人とかでこれって結構よくみられるんじゃないかと思うんですよね。心当たりありませんか?デビューしたての頃は、まぁ、それなりに可愛かったりかっこよかったりするけど、しばら
#9 仕事に集中できない?慢性的に催眠状態に陥っているかも…?
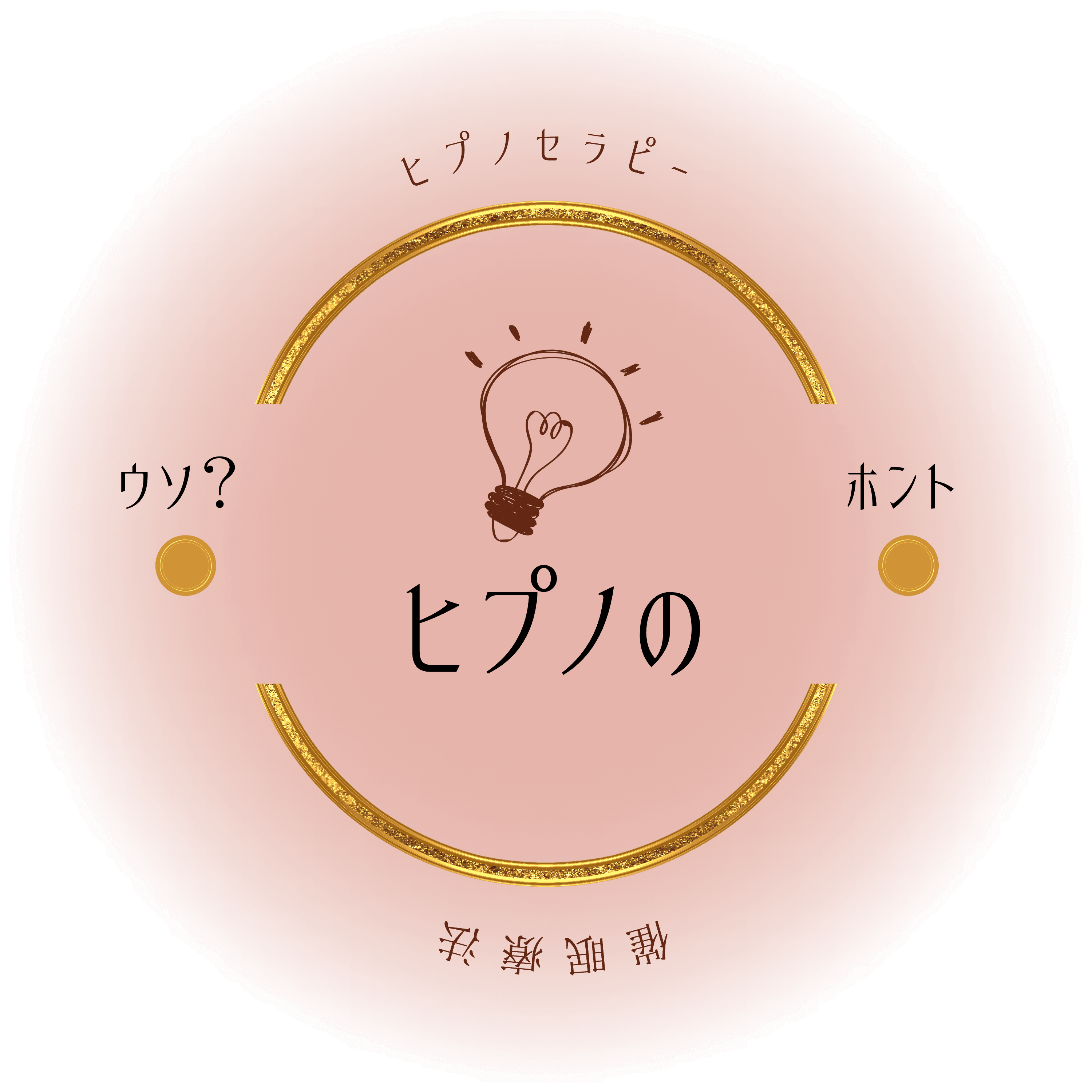
ヒプノのウソ?ホント #9 仕事に集中できない?慢性的に催眠状態に陥っているかも…? Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / Subscribe Share Amazon Anchor Apple Podcasts Spotify YouTube RSS Feed Share Link Embed
購読: Amazon |
#9 仕事に集中できない?慢性的に催眠状態に陥っているかも…?

日も短くなる=夜が長くなる。気温が下がってくるとお布団の居心地も格段と良くなってくるこの季節。やっぱり睡眠ってとっても大切ですよね。特に年末年始に向けての忙しない時期、熟睡して疲れをとるって、いつも以上に不可欠!今日は体の疲れだけではない睡眠の重要性についてです。
このエピソードのポイント
いつでもどこでも眠れた私が陥った極度の不眠、地獄の循環… 睡眠=脳のリセット。リセットがされないと… 脳のリセットの仕組み やばい催眠状態! 睡眠の質を改善した体験談 オーラリング 寝る前のルーティン 栄養バランスの改善スクリプト
ヒプノの嘘・ホント、エピソード9へようこそ。
いよいよ11月も後半に入りましたね。日も短くなってきて、ということは逆に夜が長くなっているわけですが、季節と共に睡眠時間が変わったりしますか?私は、冬の睡眠時間の方が長くなります。あんまり季節で睡眠時間が変わる人っていないのかな?ちょっと気になります。
冬の睡眠時間が長くなる理由はいくつかあるんですけど、まずはそもそも寒いのが苦手。なので、冬本番に入ると「熊のように冬眠して過ごせれば良いのに・・・」なんて思ったりもしますが、ぬくぬくのお布団にくるまるひとときが楽しみな季節でもありますね。ま、だからと言って就寝時間がすごく早まるわけでもないんですけどね。
それよりも睡眠時間が長くなる理由は朝にあるんです。私は、太陽と共に起きるのが好きなんですよね。なので、いわゆる一級の遮光カーテンのように部屋が真っ暗になるのが好きではありません。別に暗闇が苦手な訳ではないんですけど、朝日が入ってこない部屋が好きではないので、遮光性の低いカーテンを使っています。でもこれって逆に夏が大変。朝5時前には明るくなってくるので、やたらと早く目が覚めてしまう。ゆえに、そうですね。冬の睡眠時間が長くなるというよりは、夏の睡眠時間が短くなってしまうという方が正解かも。
気温が下がってくるとお布団の居心地も格段と良くなってくるこの季節。やっぱり睡眠ってとっても大切ですよね。特に年末年始に向けての忙しない時期、熟睡して疲れをとるって、いつも以上に不可欠!でね、今日は体の疲れだけではないというお話。
私たちの潜在意識とも深く関わっていて、ちゃんと睡眠がとれていないと、日中でもしょっちゅう催眠状態に陥ってしまって、思考力や判断力が鈍ってしまうよというお話です。
ここでちょっと私の個人的な体験談から。私はもともと、こと眠ることに関しては、全く何の問題もない人でした。一時期、会議通訳になりたての頃に、一晩中脳が全ての思考を訳そうとして、それを止めることができないみたいな脳疲労というか、明かに「脳が壊れた」と思えた時がありましたが、それも一晩だけのこと。それ以外は、いつでもどこでも、寝ようと思ったら眠れる人でした。
「不眠」という症状を思い知ったのは2016年に病気になった時。当時はほぼ眠れず、実際には睡眠ゼロで生きることはできないので、ごく浅い眠りには入っていたのだと思いますが、おそらく体が動くたびに症状で意識が戻るみたいなことを繰り返していたので、感覚的には一晩中起きている感じ。そして毎日、夜が来るのが怖くなりました。夜が来るのが怖いっていう感覚もね、あれが初めてでした。
体の修復も睡眠中に行われるので、睡眠がしっかり取れていないということは体も修復されないということで、回復に3年以上かかったのは、それも原因の一つだったのではないかと思っています。でもね、「睡眠が大切」と言われても、当時は何を試しても効果を感じませんでした。特に、不眠が他の症状で引き起こされているので、症状が良くならないと眠れないけど、眠れないから良くならないみたいな、地獄の循環みたいに感じていました。
今ではほぼ数分、10分ぐらい で寝付くことはできますが、真夜中に1、2度目が覚めるというのは相変わらず続いているので、未だに睡眠の質は完全には戻っていないといえます。それでもオーラリングの睡眠効率では基本的に80を超えているので、睡眠の質としては悪くありません。でも、オーラリングを使い始めた時は60から70レベルだったんです。どう改善したかについても後でちょっとご紹介しますね。
睡眠の質が関係しているのは、体の修復だけではなく、情報の整理、脳のリセットも睡眠中に行われます。そして、年末のこの忙しい時期には、クリスマス、忘年会、お正月の準備、お歳暮などなど、入ってくる情報も半端ないですし、イベントやらプレゼントやら、考えなければいけないこと、やらなければならないことも多いですから、なおさらこの毎晩のリセットが大切になってきます。
このリセットがうまくいかないとどうなるのか? こんな経験ありませんか?別に体がそう疲れてるわけでもないんだけど、なんだかぼーっとしちゃう、集中できない・・・みたいな。多分、誰でも覚えがあるのではないかと思います。要は思考力、判断力、決断力が鈍くなった状態。
これは、睡眠中のリセットがうまくいかなかったか、またはその日に特に情報量、つまり大きな出来事や衝撃的なニュース、過剰なストレスが存在したことで、意識のキャパをあっという間に超えちゃったかのどちらか、または両方になります。
どういうことかというと、私たちの意識には顕在意識と潜在意識の二つがありますよね。そして、その間にはフィルターがあります。何でもかんでも潜在意識に落ちないようにフィルターが存在するわけです。
夜、眠りに落ちると、その日に起きた出来事や入ってきた情報・刺激の整理が始まります。何が重要で何が不要なのかを見極め、重要と判断された内容は潜在意識に入り、もはや不要と判断された内容は・・・ま、自然と記憶から消えていきます。単純な例を挙げれば、数日前のお夕飯に何を食べたのか・・・もし誕生日や記念日などでおしゃれなレストランでコース料理をいただいたり、家族が自分の大好物を色々と準備してくれていたりしたら、きっと覚えていると思いますが、普段の一般的なお食事だったら、一昨日のメニューやその前後に食べたものと混乱してよく覚えていなかったりするのではないでしょうか?逆に、「またカレーだった。もううんざり」みたいに、良くも悪くも印象に残る内容は、長めに記憶に残るものです。
なので、「重要」の定義は良いこととは限りません。要は印象が強かったもの、何度も繰り返し起きていることなどが主に「重要」として潜在意識に落ちていきます。
で、この情報の整理をするということは、自分のキャパをリセットするということでもあります。要は、どれだけの情報を一時的に保管できるか
#8 脳は毎分XXXもの酸素や栄養素を必要としている!?
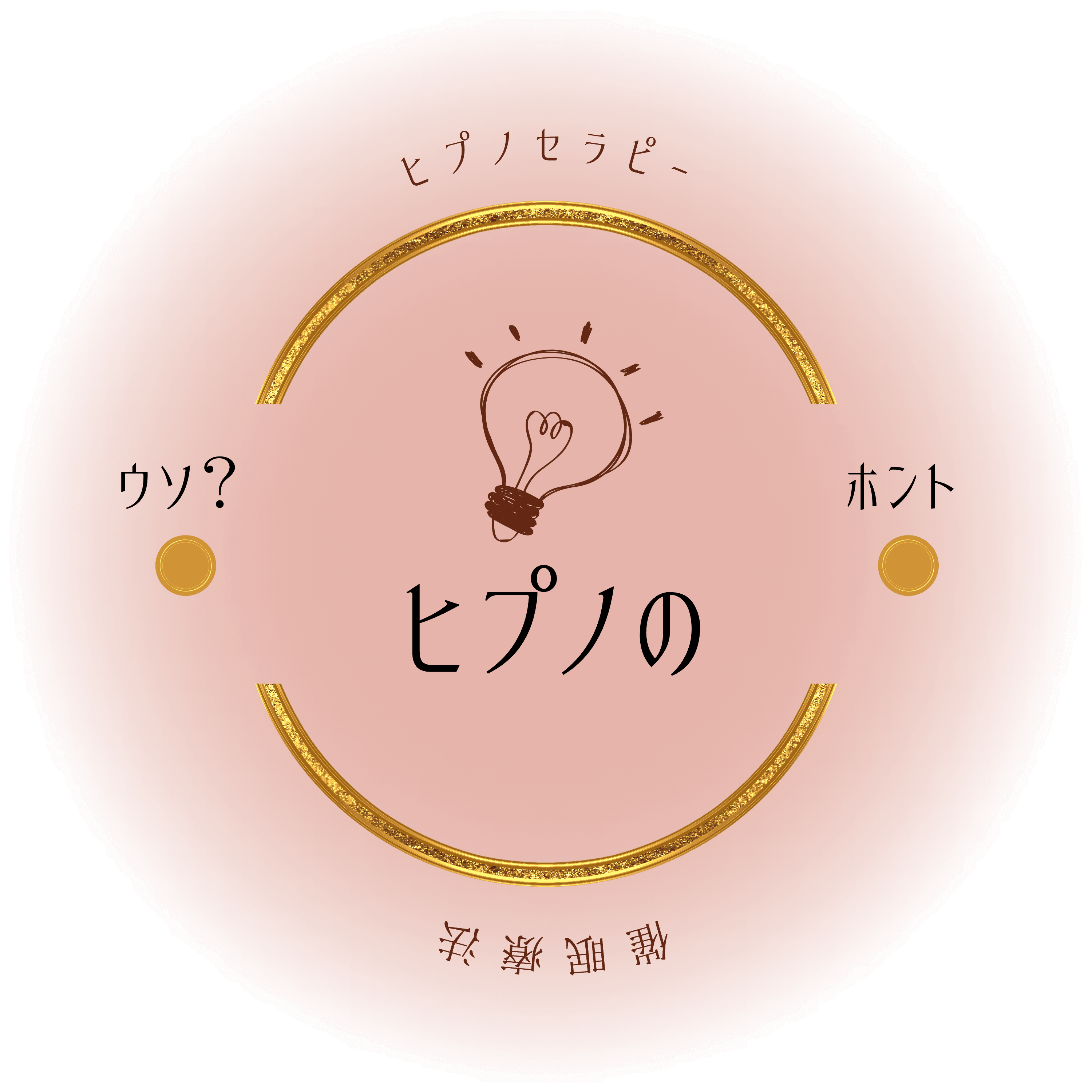
ヒプノのウソ?ホント #8 脳は毎分XXXもの酸素や栄養素を必要としている!? Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / Subscribe Share Amazon Anchor Apple Podcasts Spotify YouTube RSS Feed Share Link Embed
購読: Amazon |
#8 脳は毎分XXXもの酸素や栄養素を必要としている!?

実りの秋の真っ只中!旬の果物や野菜、楽しまれてますか?それとも…忙しくてデリバリーを頼んだり、コンビニでお弁当を買ったり、スーパーの出来合いのお惣菜に頼ってる???
その選択、日々のストレスや疲れを悪化させているかもしれませんよ。今日は、忙しい時だからこそ、ストレスを解消してエネルギー充電し、効率よく乗り越えるために、食事を見直そうという繁忙期を乗り越える方法シリーズ、第4弾です。
このエピソードのポイント
大量の酸素と栄養素を必要としている脳 脳は毎分XXXを必要としている! 例:幸せホルモン、セロトニンの生成に必要なビタミンとミネラル より多くの栄養素を脳に送り込むためには・・・ スーパーのどのエリアでお買い物?食事の質、簡単チェック これだけでも食事の質が改善! 凝った料理は不要。手間暇かけずに栄養を脳に送ろう!エピソードでご紹介した書籍 Better Brain
スクリプト
ヒプノの嘘・ホント、エピソード8へようこそ。
繁忙期を乗り越える方法シリーズ、第4弾。実りの秋の真っ只中ですが、旬の果物や野菜、楽しまれてますか?それとも、忙しくてデリバリーを頼んだり、コンビニでお弁当を買ったり、スーパーの出来合いのお惣菜に頼ってますか?
その選択、日々のストレスや疲れに影響しているかもしれませんよ。今日は、忙しい時だからこそ、ストレスを解消してエネルギー充電し、効率よく乗り越えるために、食事について考えようという話です。
それとヒプノセラピー、潜在意識と何の関係があるの?って思われるかもしれませんね。ふか〜い関係性があるんですよ。実は、私の親友がサイコセラピスト、栄養士、かつヒプノセラピストというスーパーウーマンで、数ヶ月前に彼女にとある本を勧められました。「Better Brain」ベターな脳、「より良い脳」ですかね、というタイトルで、端的にいうとビタミンとミネラルなどの栄養素のバランスが如何に脳に重要か、精神疾患の改善に有効かっていう本なんですけど、最初は「私精神疾患ないし・・・」と思ってなぜこの本を勧められたのかちょっと不思議に思ったんですね。でも、何せ信頼できる親友の言うことなので、勧められるがままに読んでみたところ・・・目から鱗!!
まずビタミンやミネラルを含む栄養素が如何に健康に重要なのかって、誰でも頭ではわかっていることだと思うんですよね。でもそれらの栄養素の脳へのインパクトって正直、私は考えたことなかったんです。しかも精神疾患、うつ病、躁鬱、ADHD、PTSDなどが改善するレベルって・・・相当なレベルじゃないですか?ただ、私にとって衝撃的だったのは、もちろんそれもあったんですけど、それよりも如何に脳が大量の栄養素を必要としているか、そしてそれらの栄養素を十分に満遍なく摂取しないと、体も心も脳も悲鳴をあげると言うことだったんですよね。
そこで、脳と栄養素の関係について、この本、Better Brainからところどころ抜粋してご紹介したいと思います。日本語版はまだ出ていないみたいですが、本の情報もショーノートに載せておきますので、ぜひ参考にされてください。
まず、毎分1リットルの血液が脳を通過しているってご存知でしたか?1リットルの血液って、人一人の全血液量の15%〜20%だそうです。でも、脳自体は体重の2%程度なので、臓器のサイズとしては比較的小さい。この比較的小さな臓器が私たちの体を流れる血液全体の15%以上を毎分必要としているという計算になります。体重の2%しか占めてない臓器が、60秒ごとに全体の20%近くもの血液を必要としている。これって大量の血液ですよね。つまり、それだけ多くの酸素と栄養素を脳が必要としているということになります。
なので、私たちの普段の食事から得ている栄養素って、もちろん筋肉を作ったりということにも使われるんですけど、それらの栄養素を運ぶ血液の2割近くは毎分、脳に行ってるということは、つまり食事から得ている栄養素の2割が脳に行っている。脳だけで2割ですよ。そのくらい、脳って大量の栄養素を必要としているっていうことで、逆にいえば、この毎分1リットルの血液に、酸素、ビタミンやミネラルがたっぷり、十二分に含まれている必要があるとも言えます。
脳って私たちが人間らしく生活するために絶対的に必要な、他の動物と異なる部分ですよね。他の動物の場合に、どの程度の血液量が毎分脳へ行くのかは私は知らないですが、人間の脳の構造自体がより複雑ですよね。脳の考え方にもいくつかあるようですが、爬虫類脳とも言われる原始的な部分、これは脳幹を指し、呼吸や心拍、生殖機能など生命を司る脳になりますので、「爬虫類」脳とも言われるぐらいですから動物なら必ず持っている脳ですね。
それだけでなく、哺乳類脳、これがいわゆる大脳辺縁系、ざっくり言えば感情や記憶を司る潜在意識の部分です。ヒプノセラピーの領域とも言えます。
そして人間脳、これが大脳新皮質、つまり思考や分析、言語などを司る顕在意識の部分で、人が人らしく生きるために発達した部分。人間に近しいと言われている猿も大脳新皮質が存在しますが、大脳新皮質の中でも前頭葉の部分で人間の方がより発達しているそうです。
改めてこの構造の違いを考えてみると、私たちの脳がより多くの栄養素が必要になるのも頷けます。特に、思考とか分析って、エネルギーが要ると思いませんか?日々曝される莫大な情報や刺激を分析して、重要性を判断して、時に決断をして・・・脳ってすっごく働き者!!事実、この本によると最も代謝が活発な臓器なのだそうです。代謝が活発ということはそれだけ化学反応が多く起きているということ。
だからこそ、夜の睡眠の質がとても大切になってくるのですが、それは次回お話しするとして、では、この代謝に、具体的にどのくらい栄養素が必要なのか、本に記載されている例をご紹介しますね。
トリプトファンという必須アミノ酸があります。「幸せホルモン」として知られているセロトニンとか体内リズムと関係して、夜、眠気を誘うホルモンであるメラトニンにもなることで知られています。
で、このトリプトファン、セロトニンへ変換されるためには酵素が必要なんですが、実は酵素があってもそこに特定のビタミンとミネラルがなければ、その酵素は役割を果たせない、つまりセロトニンへ変換できないのだそうです。そして、トリプトファンからセロトニンへの変換に必要なビタミンとミネラ
#7 繁忙期をパワフルに乗り越える方法③
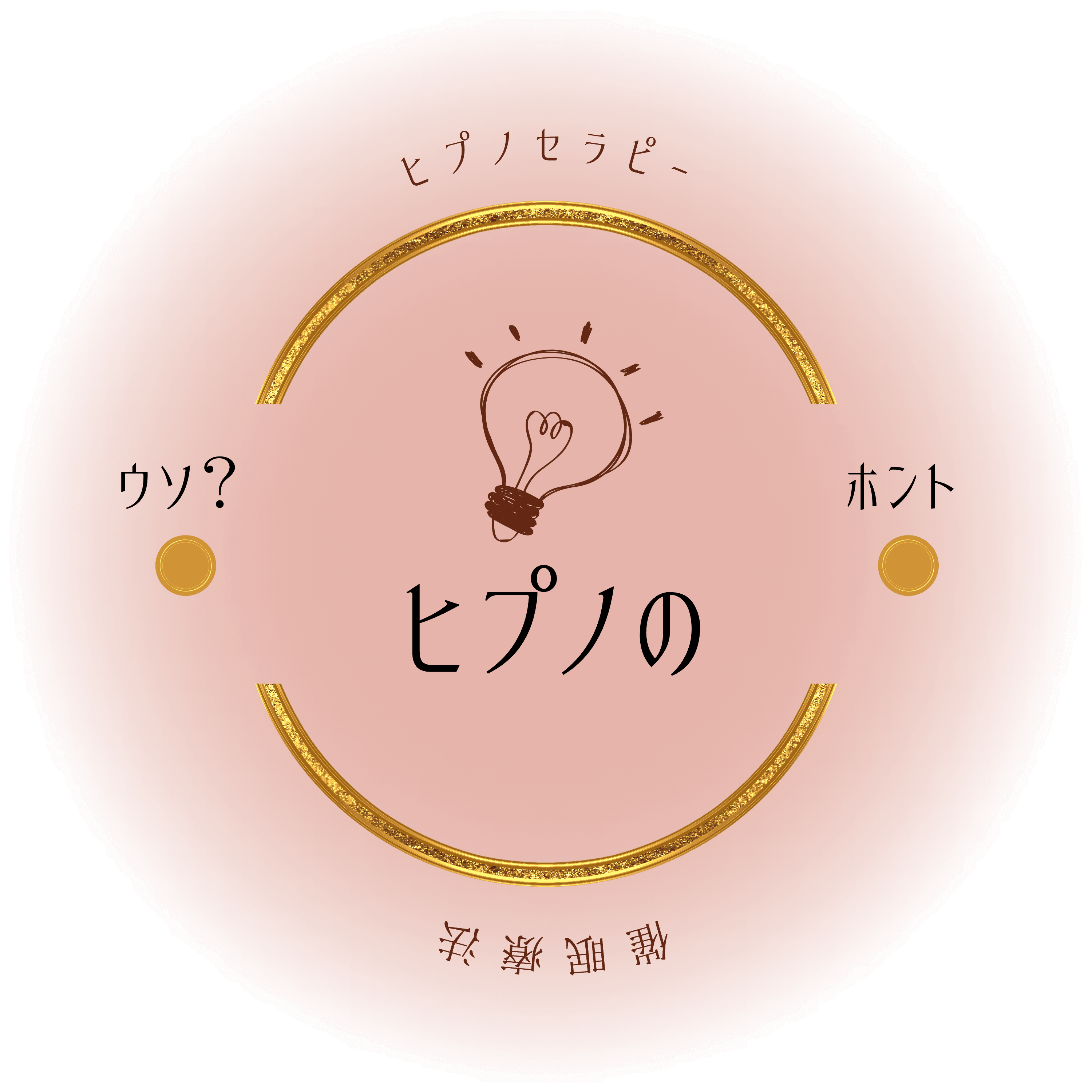
楽しいイベントも多いけれど、年末に向けてどんどん忙しさが増し、ストレスも増えがちな秋の季節。今回は、如何にストレスを溜めずに、クリアな意識で効率性を上げて、心も体もフルパワーで年末までを乗り切る方法の第3弾です。
今日の内容は第1弾、2弾とも関連していますが、忙しい時ほど自分を大切にする!と言うことと、その一つとして、小さな習慣の積み上げでセルフケア、そしてストレスを削減しようというお話です。
このエピソードのポイント
セルフケアと生存(サバイバル)本能
家族を大切にするために必須な前提条件
時間をかけないセルフケアと小さな習慣
趣味や自分のためにできることを、忙しい時でも実践する方法モーニングルーティンで1日を決めよう ガイド付きオーディオで催眠状態を体験スクリプト
ヒプノの嘘・ホント、エピソード7へようこそ。
繁忙期を乗り越える方法シリーズ、第3弾。今日の内容は第1弾、2弾とも関連しているのですが、忙しい時ほど自分を大切にする!と言うこと。その一つとして、小さな習慣の積み上げでストレスを削減しようというお話です。「自分を大切に」とか言うと、はぁ?そんな悠長なことをとか思われてしまうかもしれませんが、忙しい時こそ、自分を大切にする、ケアをすることが大切だと思うんですよね。特に日々ご家族のケアをされているあなた!そう。自分のこと、一番最後になっていませんか?自分のことだけ疎かになっていませんか?
いやいや、自分のケアもしっかりしてます?うん、素晴らしい!!やっぱりね、自分自身に余裕がないと、本当の意味で大切な人のケアをすることって難しいと思うんですよね。そもそも、人間も動物で、生存本能、サバイバルの本能があるわけですから、ぶっちゃけ本能としては自分の生き残りが一番大切なわけですよ。なので、顕在意識でどう感じていようと、最終的には自分の身を守ることが優先されるんですよね。燃え尽き症候群がその最たるものだと思います。
自分をケアしていたら、燃え尽き症候群にはならない。自分の体や心のケアより、仕事や家族や他のことを優先し続けた結果、本能が「ここまで!」って体も心もシャットダウンしちゃう。
お伝えしましたよね。最終的な決定権を握っているのは潜在意識。顕在意識はその掌の上で転がされているだけ・・・
「人を愛することができたり、人に愛されるためには、まず自分を愛する必要がある」って聞いてことありませんか?これって、その通りだと思うんですよね。自分を大切にできるって言うことは、大切にする方法を知っていると言うこと。だからこそ、周りの人も大切にできるし、周りの人を大切にするから、大切にされる。
また、自分の価値を認めることができているから、人の価値を認めることができて、そして人からも認められる。「他人軸」って言う言葉をご存知かもしれませんね。人に認められることがとても大切な人は、人に認められることで自分を認めているので、自分自身では認めてないんですよね。これはね、結構辛い状況だと思います。だって、常に誰かから認められるために努力をしているから。または誰かから認められないと自己否定をしてしまったり。
ちょっとイメージしていただきたいんですけど、大きなグラス・・・が良いかな。そこに入っているお水をご自身のエネルギーとか自分に対する愛情だと思ってください。で、本来は、そのグラスになみなみと水が注がれていて、そこから溢れ出てくる、かけ流しの温泉みたいにね、そのグラスから溢れ出てくる水、つまり愛情とかエネルギーを周りの人とシェアするっていうのが一番健全な形なんですよね。ということは、このグラスの水を常にいっぱいにしておかなければ、自分へのエネルギーや愛情も不足しちゃうわけです。下手したら、枯渇しちゃう。で、自分にも足りないお水を人に分け与えていたら・・・当然最終的には病気になったりしちゃいますよね。
ご主人やお子さんたちがご自身にとって大切であればあるほど、自分のグラスをいつも満たしておく、そして溢れるお水をご家族に提供できるのが健全な形。で、そんなの理想でしょ?って思われるかもしれませんが、私は可能だと思います。自分を大切にするって、別に自分に時間やお金をかけるっていうことではないからです。
なので、大切な人の日々のケアをされているそこのあなた!ぜひ、忙しい時ほど、短時間で良いので、セルフケアを実践されてみてくださいね。でも、それって、ストレスに任せて食べまくるとか、それはまたちょっと違う・・・ その辺りはまた、お話ししたいと思いますが、今日はその自分を大切にすると言う一環での小さな習慣ということで、本題に入りますが、このシリーズの第1弾でご紹介したタイムマネジメントも習慣ですよね。最初に設定してしまえば、週に1回30分、毎日5分程度で予定や、やるべきことを管理できる。柔軟に調整もできるので、ストレスが減る。何より、常に優先順序が何なのか、何から始めれば良いのかがクリアになっているので、気持ちに余裕が生まれます。
第2弾の短時間で、5分から20分程度しかないときに、気持ちを切り替える、リフレッシュする方法も、感情が乱れた時、ストレスを感じた時に限られた時間でできる、やればやるほどあっという間にリラックスできるようになるので、やはり習慣化することで効果が上がる内容です。
これだけでも相当違うと思いますが、余裕がおありであれば、第3弾も実践されるとよりパワフルに繁忙期を乗り越えていただけること請け合いです。
小さな習慣と言いましたが、基本的にはなんでもいいんですが、ご自身にとってしっくりくること、好きなことを忙しい時期だからこそ、時間を作って、つまり第1弾でご紹介したタイムマネジメントでもうカレンダーに最初から入れてしまうととても効果的です。と言うのも、予定に入っていれば、「時間がない」ってならないですよね。もう、そのための時間を作ってあるので。
例えば、既に毎朝、エクササイズをしているとしましょう。私の場合は朝一番、朝食の前にヨガを1時間ほどするんですが… 習慣になっていることでも、忙しくなると「あ~、もういいや」ってなりがちだったりしませんか?私はね、以前そうだったんですよ。でも、忙しい時だからこそ、ちょっとでもいいからやる。例えば15分にするとか。10分のストレッチにするとか。ストレッチだったら、それこそベッド
#7 繁忙期をパワフルに乗り越える方法③

楽しいイベントも多いけれど、年末に向けてどんどん忙しさが増し、ストレスも増えがちな秋の季節。今回は、如何にストレスを溜めずに、クリアな意識で効率性を上げて、心も体もフルパワーで年末までを乗り切る方法の第3弾です。
今日の内容は第1弾、2弾とも関連していますが、忙しい時ほど自分を大切にする!と言うことと、その一つとして、小さな習慣の積み上げでセルフケア、そしてストレスを削減しようというお話です。
このエピソードのポイント
セルフケアと生存(サバイバル)本能 家族を大切にするために必須な前提条件 時間をかけないセルフケアと小さな習慣 趣味や自分のためにできることを、忙しい時でも実践する方法 モーニングルーティンで1日を決めようスクリプト
ヒプノの嘘・ホント、エピソード7へようこそ。
繁忙期を乗り越える方法シリーズ、第3弾。今日の内容は第1弾、2弾とも関連しているのですが、忙しい時ほど自分を大切にする!と言うこと。その一つとして、小さな習慣の積み上げでストレスを削減しようというお話です。「自分を大切に」とか言うと、はぁ?そんな悠長なことをとか思われてしまうかもしれませんが、忙しい時こそ、自分を大切にする、ケアをすることが大切だと思うんですよね。特に日々ご家族のケアをされているあなた!そう。自分のこと、一番最後になっていませんか?自分のことだけ疎かになっていませんか?
いやいや、自分のケアもしっかりしてます?うん、素晴らしい!!やっぱりね、自分自身に余裕がないと、本当の意味で大切な人のケアをすることって難しいと思うんですよね。そもそも、人間も動物で、生存本能、サバイバルの本能があるわけですから、ぶっちゃけ本能としては自分の生き残りが一番大切なわけですよ。なので、顕在意識でどう感じていようと、最終的には自分の身を守ることが優先されるんですよね。燃え尽き症候群がその最たるものだと思います。
自分をケアしていたら、燃え尽き症候群にはならない。自分の体や心のケアより、仕事や家族や他のことを優先し続けた結果、本能が「ここまで!」って体も心もシャットダウンしちゃう。
お伝えしましたよね。最終的な決定権を握っているのは潜在意識。顕在意識はその掌の上で転がされているだけ・・・
「人を愛することができたり、人に愛されるためには、まず自分を愛する必要がある」って聞いてことありませんか?これって、その通りだと思うんですよね。自分を大切にできるって言うことは、大切にする方法を知っていると言うこと。だからこそ、周りの人も大切にできるし、周りの人を大切にするから、大切にされる。
また、自分の価値を認めることができているから、人の価値を認めることができて、そして人からも認められる。「他人軸」って言う言葉をご存知かもしれませんね。人に認められることがとても大切な人は、人に認められることで自分を認めているので、自分自身では認めてないんですよね。これはね、結構辛い状況だと思います。だって、常に誰かから認められるために努力をしているから。または誰かから認められないと自己否定をしてしまったり。
ちょっとイメージしていただきたいんですけど、大きなグラス・・・が良いかな。そこに入っているお水をご自身のエネルギーとか自分に対する愛情だと思ってください。で、本来は、そのグラスになみなみと水が注がれていて、そこから溢れ出てくる、かけ流しの温泉みたいにね、そのグラスから溢れ出てくる水、つまり愛情とかエネルギーを周りの人とシェアするっていうのが一番健全な形なんですよね。ということは、このグラスの水を常にいっぱいにしておかなければ、自分へのエネルギーや愛情も不足しちゃうわけです。下手したら、枯渇しちゃう。で、自分にも足りないお水を人に分け与えていたら・・・当然最終的には病気になったりしちゃいますよね。
ご主人やお子さんたちがご自身にとって大切であればあるほど、自分のグラスをいつも満たしておく、そして溢れるお水をご家族に提供できるのが健全な形。で、そんなの理想でしょ?って思われるかもしれませんが、私は可能だと思います。自分を大切にするって、別に自分に時間やお金をかけるっていうことではないからです。
なので、大切な人の日々のケアをされているそこのあなた!ぜひ、忙しい時ほど、短時間で良いので、セルフケアを実践されてみてくださいね。でも、それって、ストレスに任せて食べまくるとか、それはまたちょっと違う・・・ その辺りはまた、お話ししたいと思いますが、今日はその自分を大切にすると言う一環での小さな習慣ということで、本題に入りますが、
このシリーズの第1弾でご紹介したタイムマネジメントも習慣ですよね。最初に設定してしまえば、週に1回30分、毎日5分程度で予定や、やるべきことを管理できる。柔軟に調整もできるので、ストレスが減る。何より、常に優先順序が何なのか、何から始めれば良いのかがクリアになっているので、気持ちに余裕が生まれます。
第2弾の短時間で、5分から20分程度しかないときに、気持ちを切り替える、リフレッシュする方法も、感情が乱れた時、ストレスを感じた時に限られた時間でできる、やればやるほどあっという間にリラックスできるようになるので、やはり習慣化することで効果が上がる内容です。
これだけでも相当違うと思いますが、余裕がおありであれば、第3弾も実践されるとよりパワフルに繁忙期を乗り越えていただけること請け合いです。
小さな習慣と言いましたが、基本的にはなんでもいいんですが、ご自身にとってしっくりくること、好きなことを忙しい時期だからこそ、時間を作って、つまり第1弾でご紹介したタイムマネジメントでもうカレンダーに最初から入れてしまうととても効果的です。と言うのも、予定に入っていれば、「時間がない」ってならないですよね。もう、そのための時間を作ってあるので。
例えば、既に毎朝、エクササイズをしているとしましょう。私の場合は朝一番、朝食の前にヨガを1時間ほどするんですが… 習慣になっていることでも、忙しくなると「あ~、もういいや」ってなりがちだったりしませんか?私はね、以前そうだったんですよ。でも、忙しい時だからこそ、ちょっとでもいいからやる。例えば15分にするとか。10分のストレッチにするとか。ストレッチだったら、それこそベッドの上でさえできてしまうので、やらない理由がもはやない・・・。なので、ちょっと寝過ごしてしまった!なんていう日も、ヨガの時間を短くすればキャッチアップできる。次の予定は遅れなくて済む。
もちろん、もう完全に寝坊しちゃった日とかもたまにあります。または体調がすぐれない日とか、時々できない日などもがあってもいいと思うんですよね。誰
#6 繁忙期をパワフルに乗り越える方法②

楽しいイベントも多いけれど、年末に向けてどんどん忙しさが増し、ストレスも増えがちな秋の季節。今回は、如何にストレスを溜めずに、クリアな意識で効率性を上げて、心も体もフルパワーで年末までを乗り切る方法の第2弾です。
前回は、毎日たった5分程度で、常に優先順序がクリアで、毎週、毎日何をすれば良いのかが明確になるタイムマネジメントをご紹介しましたが、それでも日々、いろんなことが起きて、感情が揺れることもあると思います。今回はそんな時に使えるツールのご紹介です。
このエピソードのポイント
感情には良いも悪いもない 感情に反応するか、対応するかの違い 感情が揺れうごいた時のツール 数分しかない時 5分程度時間が取れる時 20分程度時間が取れる時スクリプト
ヒプノの嘘・ホント、エピソード6へようこそ。
前回は、特に忙しい時期でも気持ちに余裕を持って、やる必要があることを確実にこなし、効率的に時間を過ごせるタイムマネジメントの方法をご紹介しました。この方法を使うと、本当に日々の焦りやストレスを減らすことができますが、それでも慌ただしく過ぎていく時間の中で、アップアップ状態になることもあるかと思います。
それも当然のことなんですよね。人間は感情の動物ですし、そもそも焦り、イライラ、不安などの感情も必要だから存在します。正直、いらない感情ってないんですよね。怒りとか憎しみ、嫉妬とかね、一般的に「悪い感情」と言われるものでさえ、自分の身を守るために存在する重要な感情で、ちゃんと役割があるっていうことなんですね。
なので、感情自体には良い悪いはありません。それらの感情を感じたときに、どう対応するか、対応できるかで、ご自身の言動が適切か、不適切かが分かれてくるのだと思います。その場の状況によっても、何が適切、不適切というのは一定程度変わるかもしれませんが、基本的には、感情のままに「反応」しているのか「対応」しているのかにかかっていると思います。
どういうことかというと、反応している時っていうのは、そこに判断や思考がなくて、感情が湧いたままに自動的に何か言ってしまう、行動してしまうっていうこと。言い換えると、顕在意識が機能していなくて、潜在意識に存在している紐付け、パターンを基に自分を守ろうとする言動を咄嗟に取ってしまっています。
例えば部下がまた書類でミスをしてしまった時に、つい「カチン」ときて、「もう、これ何度目?」なんて、ちょっときつい口調で言ってしまう。これが反応しているパターン。
逆に対応している時っていうのは、感情が湧いた後、行動をとる前に思考や判断が入るんですよね。通常は、感情とちょっと距離を置くことから始まります。例えば先ほどの例なら、「あ、またミスってる。ったくもう」って思った時に、「同じミス何度もされると、どうもカチンとくるのよね」って客観的に自分の感情を見る。で、どう対応したいかを考える。「XXXさん、この書類なんだけど、ミスを起こしやすい部分ってどこなのかな?分かりづらい部分とか、ここがこうなっていればミスを防げるとか、どう思う?」と解決策を模索するとか。自分の感情を認めた上で、対応しているわけです。
今日は、繁忙期をパワフルに乗り越える方法第二弾、感情が乱れた時に短時間で簡単に実践できる対処方法をお伝えしたいと思います。時間が数分しかない時、5分程度ある時、20分程度ある時に分けてご紹介していきます。まずは、数分しかかからない方法から。先ほど、感情のままに反応するのではなく、感情に気づいて距離を置くということをお伝えしましたが、これにとても有効なのが深呼吸です。
この呼吸、侮れないんですよね。よくね「呼吸法が大切」って言われますよね。でも私自身、元々すごく呼吸が浅くて、実際「息してる?」って聞かれたこともあるぐらいで・・・ で、ヒプノを勉強する前までは呼吸法なんて言われても「ふ~ん」って思うだけで、真剣に捉えたこともなかったんですけど、ヒプノを通じて意識の仕組みや自律神経、呼吸について、学ぶだけでなく実際に体感するようになって、呼吸の重要性を心底理解することができたんですよね。なので、懐疑的に思っていても、ぜひ、しばらく試してみてください。本当に違いますから。
なので、忙しい時に感情が乱れたら、まずは深呼吸。呼吸は自律神経と繋がっていて、息を吸う方は交感神経、そして息を吐く方が副交感神経なんだそうです。なので、ちょっと興奮したり、イラッとしたり、カチンときたりしたときに、落ち着きたいと思ったら、息を吐くほうにフォーカスをして深呼吸をしましょう。
呼吸法でもありますよね。2倍の時間をかけて息を吐くみたいな。4で吸って8で吐くみたいなね。あれです。あの理由は副交感神経、つまりリラックス神経を刺激したいからなんですね。
特に対人関係で感情が揺れた場合には、場所を変えると良いですね。タイムアウトみたいな。その場を離れてちょっと外に出るとか、トイレに行くとか。できれば緑がある場所だとなお良いですよね~ なので、お庭に出てみるとか、または 庭が見える場所に行くとか。職場で外に緑があるようなら、使わない手はないですね。
3回ゆったりと深い呼吸をするだけでも違いますし、もう本当に数分もかからないですよね。電車などの遅延で、約束に遅れそう!!みたいにパニクりそうになる時、深呼吸する暇も惜しいって思うかもしれませんが、逆に深呼吸をすることで頭が冴えて、例えば違うルートとかを思いつくとか、とりあえず落ち着いて相手側に連絡をするとか、対応が変わってきますよ。
次に、5分程度時間がとれる場合… もう少し時間がとれるなら、深呼吸に加えて簡単イメージングをやってみましょう。これはできれば座っている状態がベスト。職場ならご自身のデスクで、腕や脚を組まずに椅子に腰掛ける感じでOK。目を閉じることで、リラックス感が増します。オフィス環境では、目を閉じて椅子に座っていることに違和感を感じる場合は、デスクに上半身うつ伏せるような感じでも大丈夫。両肘を左右に開いて、両手を重ねてそこに額を休ませるみたいな。要は、腕や脚を組まずに、力を抜けるような姿勢であればOKなので、できれば目を閉じて、まずは先ほどもお伝えした深呼吸。
目を閉じるとリラックス感が増す理由は、目から入ってくる情報、視覚の情報って膨大なんですよね。その視覚情報をシャットアウトするだけで、ストレスを減らすことができるんですよね。先ほどの数分しかなくて深呼吸だけする時でも、もし目を閉じることができれば、その方が効果的だと思いますよ。
で、リラックスできるポジションで目を閉じて深呼吸を数回したら、ここからちょっとしたイメージングに入ります。要は
#5 繁忙期をフルパワーで乗り越える方法①

楽しいイベントも多いけれど、年末に向けてどんどん忙しさが増し、ストレスも増えがちな秋の季節。今回は5回のシリーズで、如何にストレスを溜めずに、クリアな意識で効率性を上げて、心も体もフルパワーで年末までを乗り切る方法をお伝えしていきたいと思います。
第一弾は、やることの多さから時間に追われてアップアップ状態…ではなく、常に優先順序がクリアで、毎週、毎日何をすれば良いのかが明確になるタイムマネジメント、しかも毎日5分程度しかかからない方法をお伝えします。
このエピソードのポイント
プランニングに必要なもの 最初のステップ:優先事項の決め方とマイルストーンの設定 毎週やること:週に1度30分のプランニングで週の優先事項を明確に 毎日やること:毎日5分程度で、その日の振り返りと翌日の準備スクリプト
ヒプノの嘘・ホント、エピソード5へようこそ。
さて、2023年もあっという間に過ぎていきますね。年々、時間が過ぎていくのが早くなる気がしているのは私だけでしょうか?
さて、秋といえば、食欲の秋、スポーツの秋、などいろいろな「秋」がありますが、何かと行事やイベントが多い時期ですよね。お子さんがいらっしゃれば学校の行事も多い時期ですし、仕事でも年末の繁忙期に向けてさまざまな準備が本格化したり、展示会や新製品発表会などもたくさんある時期だと思います。
楽しいイベントも多いけれど、年末に向けてどんどん忙しさが増し、ストレスも増えがちな時期ではないでしょうか?ということで、今回は5回のシリーズで、如何にストレスを溜めずに、クリアな意識で効率性を上げて、心も体もフルパワーで年末までを乗り切る方法をお伝えしていきたいと思います。
ということで、今日はその第一弾。忙しさがどんどん増して、やらなければいけないことが山積みになってくると、どうしても量に圧倒されてしまって、身動きが取れなくなったりしませんか?
そんなことにならないためのプランニング、タイムマネジメントの方法をご紹介します。ご自身のスタイルに合わせて柔軟に変えることができます。このプロセス、面倒臭い、時間がかかりそうと思われるかもしれませんが、実際にはそんなに時間はかかりません。最初のステップは1時間ぐらいはかかるかもしれませんが、あとは週に1回30分程度、そして日々、5分10分程度しかかかりません。これをするだけで、日々のストレスが圧倒的に減りますので、ぜひ試してみてください。これは私は普段から好んで使っているfull focusシステムをアレンジした方法になります。
必要なものはカレンダー手帳。マンスリーとデイリーがあるものを用意しましょう。無料でテンプレートをダウンロードして印刷できるようなものもありますから、お金をかける必要もありません。プラスTodo listがあると便利です。TrelloやAsanaなどのタスク管理アプリでも良いですし、スマホやタブレットに標準で入っているto do listでも大丈夫。今回は特に、短期間であれもこれもしなければいけない状況での活用方法をお伝えしていきますが、もちろん普段使いもできます。ちなみに私は、デジタルプランナーとtrelloを愛用しています。Trelloは無料プランでも十分に活用できます。
ちょっと話がそれますが、最近はサブスクタイプのサービスがすごく増えてますよね。で、一つ一つはそんなに大きな金額ではなくても、積み上がっていくと毎月結構な額になってしまいます。で、色々とアプリを探していると「無料」とかって説明があって調べてみると、一応無料プランはあるけど、制限多過ぎてお試し程度しか使えない・・・みたいなサービスが割と多いんですよね。でも、Trelloは自動化のコマンドをたくさん使わない限り、おそらくずっと無料プランで大丈夫です。
短期的に使うだけなら、いわゆるシンプルなto do listで十分です。
ではまず、期間を区切りましょう。今回は特に忙しい時期にフォーカスしているので、ま、年末までとか、このプロジェクトが終わるまで、とか。
次に、その期間での重要なプロジェクト、イベント、目標を3つ程度に絞ります。多すぎるとフォーカスがブレてしまうので、最重要なものを3つ程度選択しましょう。他のことをおざなりにする訳ではないのでご心配なく。フォーカスがはっきりしていれば、やらなければいけないことに圧倒されて焦ったりすることが少なくなり、気持ちに余裕が生まれれば他のことに気を配る余裕も、忘れずに予定に入れることもできます。ここで選ぶのは、ある程度準備が必要だったり、達成するのに少し時間がかかったり、幾つものプロセスや工程があるもの、いわゆる3大フォーカスです。
3大フォーカスを選んだら、大まかなプロセス、特に締切日や、重要なステップを書き出していきましょう。この段階では、細かいステップである必要はありませんし、全て洗い出す必要もありません。マイルストーン、要所要所のステップとかプロセス、工程を書き出しましょう。
なので、例えば3つのフォーカスのうちの1つとして12月15日の会議での重要なプレゼンがあるとしましょう。締切日は当然12月15日、ステップとしては、「アウトラインを決定する」「必要な資料を揃える」「スクリプトを仕上げる」「スライドの完成」「最終確認・レビュー」などなど。
次に、イベントの日、締切日など日付が決まっている内容をマンスリーのカレンダーに書き出していきます。また、3大フォーカスではないけれども、すでに入っている予定や、また重要事項も書き出していきましょう。例えば、家族の誕生日であるとか、出張、習い事であるとか・・・
その後に、先ほど書き出した3大フォーカスの重要なステップやプロセスを、締切日から逆算していつまでに達成する必要があるか決めて、判断してマンスリーカレンダーに書いていきましょう。
なので、例えば先ほどの12月15日の重要なプレゼンの例であれば、まず「最終プレゼン」とマンスリーカレンダーの12月15日の欄に書きます。その後に、12月15日から逆算して、例えば、「プレゼン内容の最終確認、レビュー」を12月1日に設定して、スライドの完成を11月20日にするとか。そんな感じです。
もちろん、作業が進むにつれて、その進捗状況に応じて調整はできますから、変更不可なわけではありません。この多少の「調整が必要になる」ことから、私はデジタルプランナーなどのデジタル製品が好きです。書いた内容を消す必要もなく、新しい日付に移動させるだけで済むので。ただ、後から変えられるからと適当に決めるのではなく、現時点で現実的、妥当と思われるプランニングにしましょう。
さて、ここまでは一気におそらくできると思います。ここからは
#4 最大限の効果を得るためには…

効率よく効果を出せるヒプノセラピーですが、じゃあ、セッションを受けたらあとは何もしなくても効果が出るの?そんな疑問にお答えします。
このエピソードのポイント
ヒプノセラピーは協働作業(コラボワーク) セラピストの役割 ご自身の役割 補強と実践 ヒプノを使わずに潜在意識にアプローチするコツスクリプト
ご自身の言動の最終決定権を完全に握っている潜在意識。自分の意識、顕在意識で考えたり判断していると思っているけど、実はその顕在意識は潜在意識の掌の上で転がされているようなものというお話を前回しました。
なので、いくら自分が「人前で堂々と実力を発揮できるようになりたい」と強く思っていても、それはあくまでも顕在意識の話で、潜在意識が「いやいや、それは危険すぎるよ」と思っていたら、どれだけ強く願おうとも実現はしないという話ですよね。
じゃあどうしたらその潜在意識の内容を変えられるのか?という点で、誰でも簡単にできる方法として反復、繰り返す、言い換えれば練習すれば良いというお話を、イメージ療法などの例を挙げてご紹介しました。
で、ヒプノ、催眠を使うと早いよ、効率的に効果的に結果を出せるよというお話を、他の療法との比較とも交えてさせていただきましたが、じゃあ、ヒプノを使ったら反復は必要ないの?という疑問がもしかしたら浮かんだかもしれません。
今日はこの点についてお伝えしたいと思います。最後に、ヒプノを使わずにご自身で潜在意識にアプローチする際のコツもお伝えしますので、お楽しみに。
ぶっちゃけ、ヒプノは魔法の杖ではありません。セッションを受けたら「あら不思議。翌日から人前に立つことが平気になった」というわけにはいかないことが多いです。多い・・・というのは、実際1回のセッションで問題が解決してしまうこともあるんです。が、確率的には高くはありません。というのも、ほとんどの場合、恐怖や不安が長い間蓄積し、補強されちゃっているからなんですね。
とはいえ、前回もお伝えしたように、他の療法と比べてもヒプノでは圧倒的に早く効果が出ることも事実ですが。
ヒプノセラピーは協働作業です。ポッドキャストだとね、漢字が見えないですけどね、いわゆるコラボワーク?ですね。どういうことかというと、セラピストが潜在意識担当で、ご自身が顕在意識担当。
はぁ?ってなりますよね。あがり症の例をとって説明しましょう。
ここで早速、ご自身の想像力を使ってみてください。ご自身の潜在意識の中に鬱蒼とした森があるとして、この鬱蒼とした森が、ご自身が持っているジレンマ、悩みを象徴していると思ってください。あがり症の例であれば、この鬱蒼とした森が「人前に出るのは怖い、失敗したら大変、批判されるのが怖い」などの現状を象徴しているとします。このいかにもどんよりとした不安とか恐怖の森を変えたいわけですよね。
ヒプノセラピーではセラピストが潜在意識担当と言いました。なので、この鬱蒼とした森の中に、セッションで苗を植えます。鬱蒼とした森の中に植えられる苗を想像してみてくださいね。この苗はご自身が願っている内容を象徴しています。なので、あがり症の例なら「自分の知識をたくさんの人と共有できるのってワクワクする、皆さんのお役に立てる、楽しい」とか。
ここでちょっと話がそれますが、催眠状態を活用しない場合は、この苗を植えること自体にすっごく時間がかかるということです。フィルターを突破して植えなければならないわけですけど、その突破するのに時間がかかる、反復が必要とお話ししましたよね。
で、ヒプノでは催眠状態に入っている間、つまりフィルターが開いている間にこの苗を植えることができるわけですけど、さて、さらに想像してみてくださいね。
鬱蒼と生い茂る森の中に植えられた苗、何もしなかったら、苗の世話をしなかったらどうなると思いますか?日も当たらず、水も栄養分も周りに生い茂る大きな草木たちに取られ・・・大きく育つのは至難の業・・・
同じことで、せっかく催眠状態で、ご自身が望んでいる内容、あがり症の例なら「自分の知識をたくさんの人と共有できるのってワクワクする、皆さんのお役に立てる、楽しい」というパターン、紐付けを潜在意識に落としても、セッション後の日々の生活の中で何もしなければ、この新しいパターン、紐付けはどんどん薄れて、1週間程度で消えてしまいます。
逆に、この小さな苗をせっせとお世話したらどうでしょう?周りの草などを取り払って、日があたるようにして、せっせとお水をあげて・・・その苗が大きく育つ確率が格段と上がりますよね。
これが先ほどお伝えした、ご自身が顕在意識担当ですよというところです。
ヒプノセラピーのセッションでも、セッション後の日々の生活の中で、潜在意識に落とした新しい紐付け、パターン、ご自身が願っている内容を補強していくということがとても重要になってきます。ご自身の願っている内容のこの苗がどんどん大きくなっていけばいくほど、鬱蒼としていた森はどんどん小さくなっていきます。
じゃあ、どうやって補強していくの?っていう話ですが、いくつかの方法がありますので、それらをご紹介していきますね。
まずはMP3の活用です。これはヒプノセラピーを受ける場所によって異なると思いますが、私の場合は、セッションの後半、つまり実際に催眠に入っていただく部分ですね。この部分 は基本的に録音しています。活用するツールに内容によって、録音しないこともありますが、基本的にはいつも録音しています。そして、セッション後にMP3ファイルの形でお送りしています。
このMP3を聞いていただくというのがまず補強の一つになります。目安として最初の1週間程度は毎日聴いていただけると良いかなと思います。セッションの内容をそのまま録音してありますから、聞くたびにセッションを受けているのと同じ・・・ではないですけど、ま、近いですよね。
ですがこれだけではちょっと不十分。というのも、わたしたちって、実行に移して初めて体得しますよね。例えば、新しい機器・・・家電でもなんでも良いんですけど、使い慣れていない新しい製品を買ったとして、一度取説を読んだだけで1週間後に、使い方を正確に覚えていると思いますか?もちろんね、スタートボタンを押せばいいだけみたいな商品ならできるでしょうけどね。
普通は、実際に自分でやってみて、試してみて、初めて体得すると思います。行った事がない場所に地図頼りに行く場合。もちろん、今ではナビというとっても便利なアプリがありますけど、最初に一度見ただけで、迷わず行けますか?ぶっちゃけ私は無理です。ナビでさえ、常に自分の現在位置と、進む方向を確認